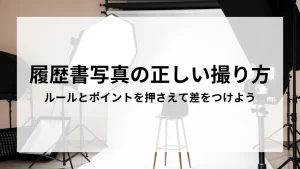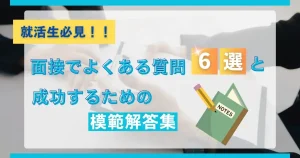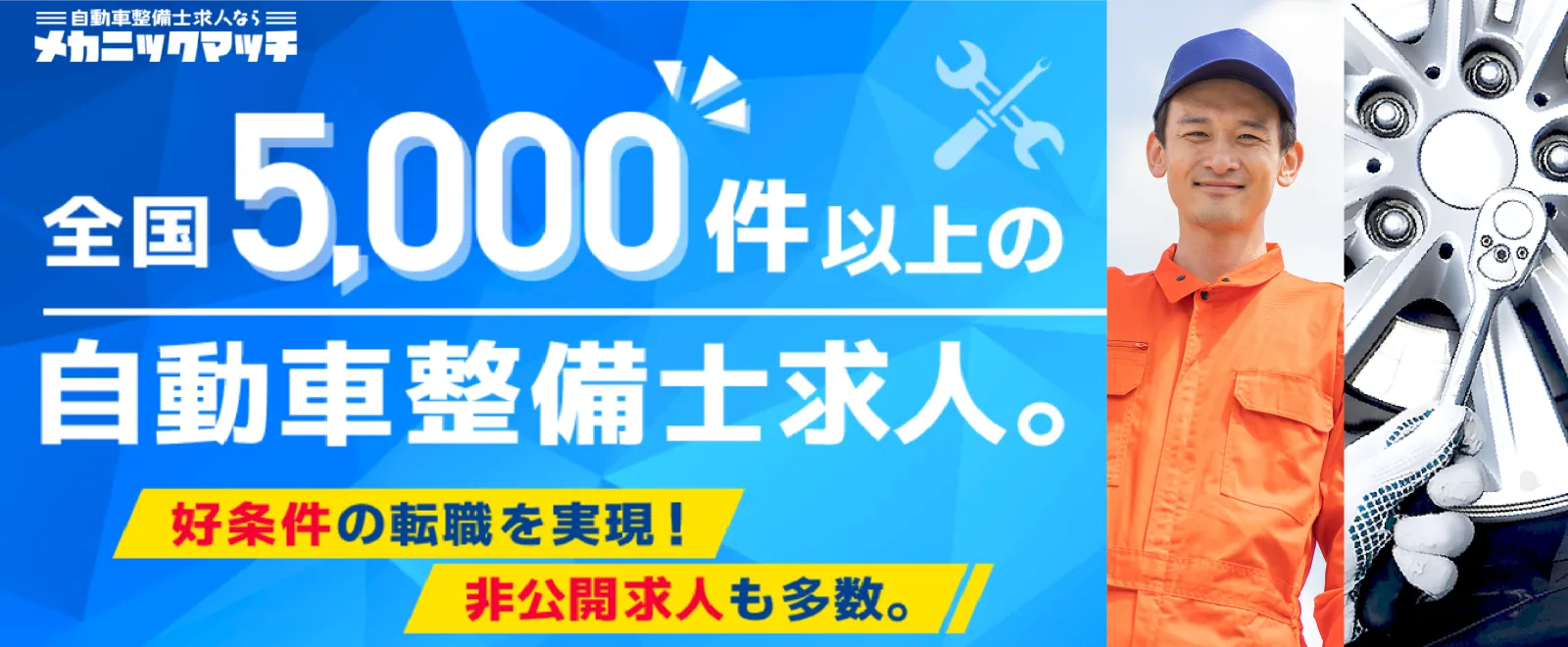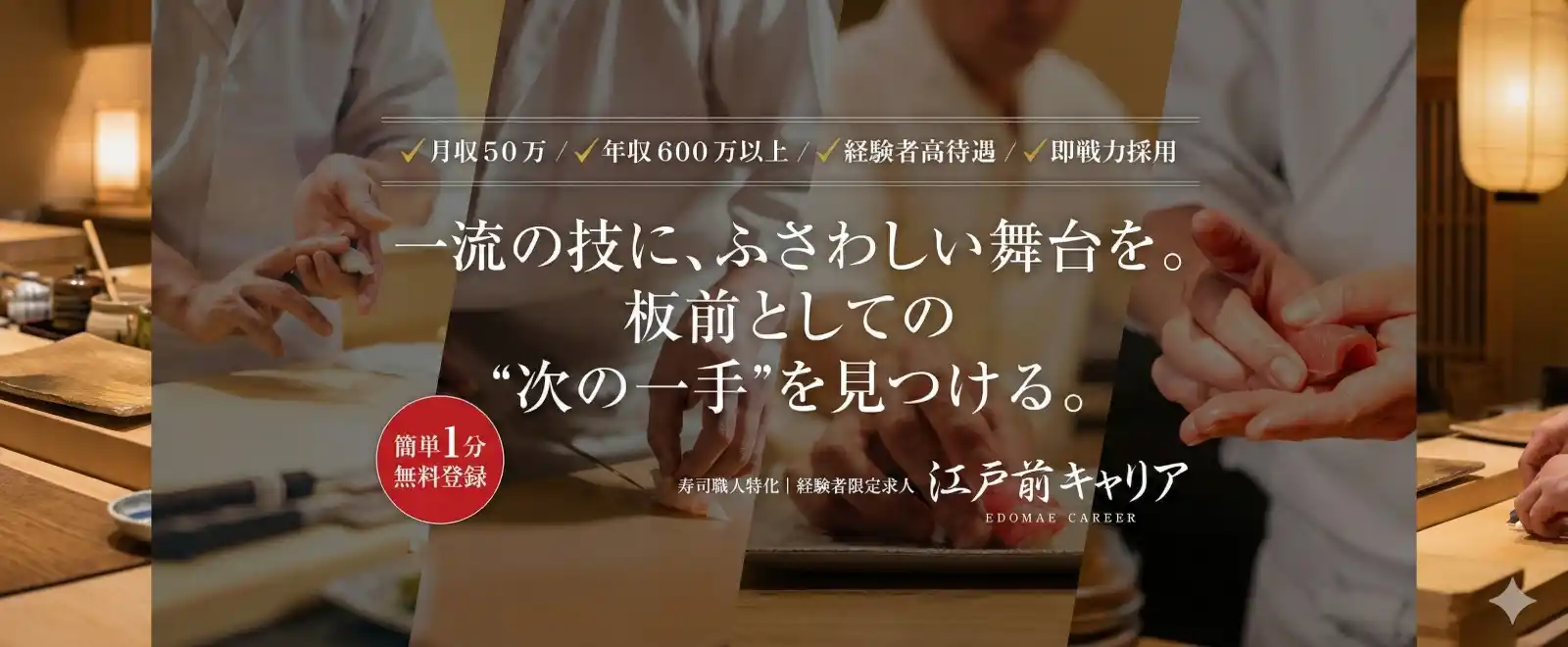就職活動は、多くの学生にとって人生で初めて経験する大きな挑戦です。
希望する企業から内定をもらうまでの道のりは長く、時には不安や焦りに押しつぶされそうになることもあります。
そんな中、「他の就活生はどんなことで悩んでいるのだろう?」と気になる人も多いでしょう。
本記事では、就活生が抱える悩みをランキング形式で紹介し、その解決方法について具体的に解説します。
この記事を参考に、就職の悩みと解決方法を理解し、就職活動を有利に進めましょう。

就職活動の悩みランキング【TOP10】

就職活動を進めていくうえで、大小問わず悩みは必ずでてきます。
では、就活生はどのようなことに悩んでいるのでしょうか。
ここからは、就職活動の悩みをランキング形式で紹介します。
就職活動や転職活動の悩みを専門家に相談したい方は、こちらのサービスをご検討ください。
第1位:自分に合った業界や職種が分からない
就職活動では、自分に合った業界や職種がわからず悩む学生が多く存在します。
多くの就活生は、社会人経験がありません。
そのため、仕事内容や働き方を具体的に想像しにくくなります。
また、情報量が膨大なため、自分に必要な情報を取捨選択しなければなりません。
さらに、周囲の意見や世間的なイメージに影響され、自分の本当の適性を見失うこともあります。
自分に合った職業や職種を就活や転職のプロに紹介してほしい方は、こちらのサービスもご検討ください。
-1024x341.webp)
\ 新卒求人サイト /
.webp)
\ 新卒求人サイト /
-1024x341.webp)
\ 飲食業界求人サイト/
-.webp)
\飲食業界求人サイト/

\ 整備士求人サイト /
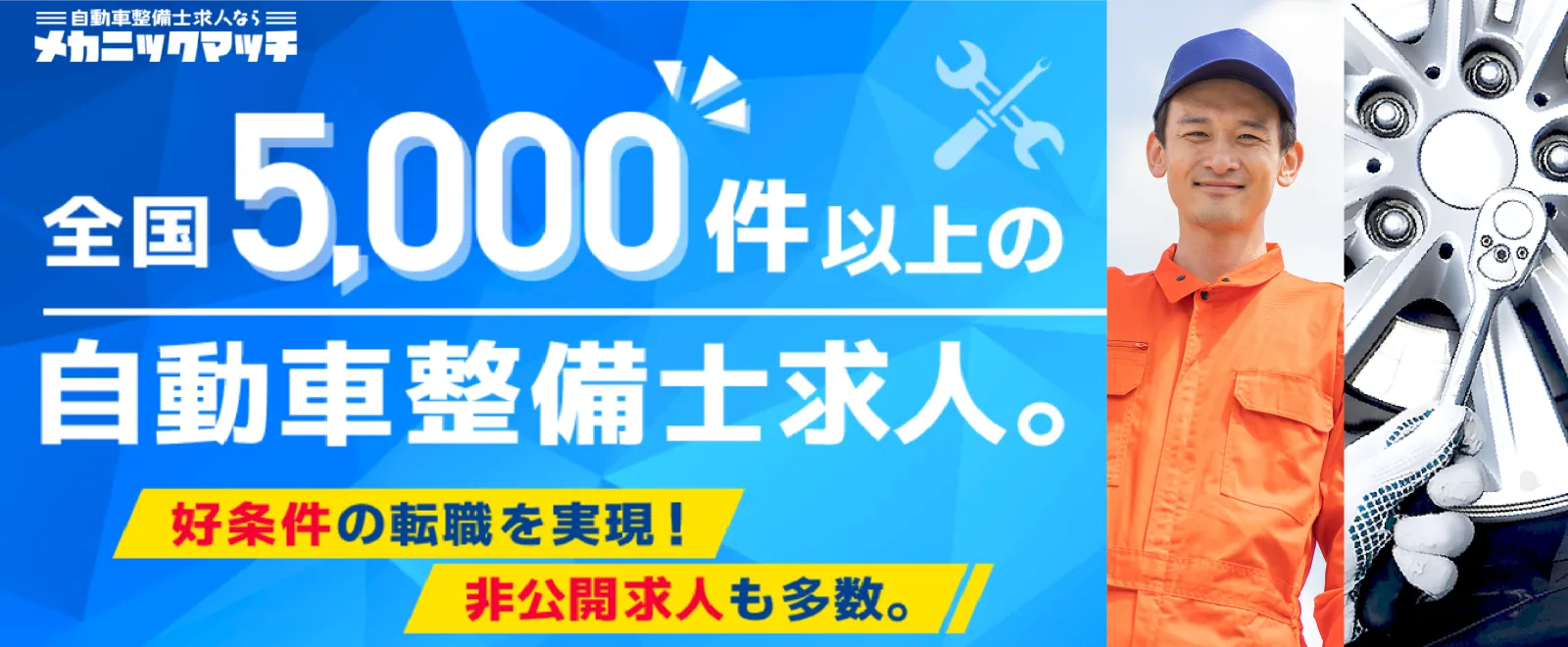
\ 整備士求人サイト /

\ 寿司職人求人サイト /

\ 寿司職人求人サイト /
第2位:面接でうまく話せない
面接でうまく話せないことに悩む学生は少なくありません。
面接という非日常的な場面に緊張してしまい、頭が真っ白になることがあります。
また、準備不足で自己PRや志望動機を整理できていないため、言葉がまとまらないこともあります。
さらに、採用担当者の反応を気にしすぎて、自信を持って自分の考えを伝えられなくなることも面接でうまく話せない原因のひとつです。
第3位:エントリーシートが通らない
就職活動では、エントリーシートが通らないことに悩む学生が多く見られます。
就職活動では、複数の企業に向けてエントリーシートを提出しなければなりません。
複数企業のエントリーシートを一気に作成すると、抽象的で他の企業にも当てはまる内容になってしまうことがあります。
また、自己PRに具体性や成果が欠けており、説得力を持たせられないケースも少なくありません。
さらに、表現が曖昧で読み手に印象を残せず、数多くの応募の中で埋もれてしまうこともあります。
第4位:内定が出ない
就職活動では、内定が出ないことに悩む学生が数多く存在します。
一例として、志望業界や企業を絞りすぎて、チャンスを狭めてしまうことがあります。
また、面接やエントリーシートでのアピールが不十分で、採用担当者の印象に残らないことも少なくありません。
さらに、選考での失敗を振り返らず改善できないことが、結果的に繰り返し不採用につながる要因となります。
第5位:周囲と比較されて落ち込む
就職活動では、周囲と比較されて落ち込むことに悩む学生が少なくありません。
一例として、友人や同級生が内定を得ると、自分が遅れているように感じて焦りを募らせることがあります。
また、SNSなどで成功体験だけが目に入ることで、現実以上に差を意識してしまうこともあるでしょう。
その結果、自分の努力や成長を正しく評価できず、自己肯定感が下がります。
第6位:自己PRが思いつかない
就職活動では、自己PRが思いつかないことに悩む学生が少なくありません。
一例として、自己分析で過去を振り返った際、特別な経験がないと感じ、自分にはアピールできる強みがないと思い込んでしまうことがあります。
また、アルバイトやサークル活動など身近な体験を価値あるエピソードとして認識できないこともあります。
さらに、自分の成果を客観的に整理する力が不足しており、言葉にできないことも自己PRが思いつかない原因のひとつです。
第7位:企業研究がうまくできない
就職活動では、企業研究がうまくできないことに悩む学生が多く存在します。
企業研究は、事業内容や経営理念などを網羅的にインプットしなければなりません。
しかし、どこに注目すべきかわからず表面的な理解にとどまってしまうことがあります。
また、公式サイトの内容だけでは実際の働き方や社風が見えにくく、志望動機に深みを持たせられないこともあります。
さらに、競合との違いを整理できず、自分なりの志望理由を説得力ある形で伝えられないことも企業研究がうまくできない原因のひとつです。
第8位:キャリアプランが描けない
就職活動では、キャリアプランが描けないことに悩む学生が少なくありません。
ほとんどの就活生は、社会人経験がありません。
そのため、将来の仕事や成長のイメージを具体的に持ちにくいことがあります。
また、情報収集しても企業説明が抽象的で、自分の未来像に結び付けられないこともあるでしょう。
さらに、自分の価値観や優先順位を整理できていないことが、将来の方向性を不明確にする原因になります。
第9位:就活と学業・プライベートとの両立が難しい
内閣府の調査では、2024年度時点で、48.3%の就活生が就活の始まりから終わりまで9カ月程度以上かかったと回答しました。
就活と学業・プライベートとの両立が難しいことに悩む学生は少なくありません。
説明会や面接の予定が立て込むと、授業や卒業論文とのスケジュールが衝突してしまうことがあります。
また、限られた時間で優先順位をつけられず、どちらも中途半端になってしまうことも少なくありません。
さらに、無理な生活リズムが続くことで、体調や精神面に負担がかかり、集中力を保てないことがあります。
第10位:親や周囲からのプレッシャー
株式会社マイナビによると、2024年時点で子供の就職活動に「高い関心がある」または「関心があった」と回答した保護者は、70%いました。
また、同調査で56.9%の保護者が子供の就職活動に対して不安を感じていると回答しました。
就職活動では、親や周囲からのプレッシャーに悩む学生が少なくありません。
一例として、「安定した企業に入るべき」や「大手企業を目指すべき」といった期待が、重圧としてのしかかることがあります。
また、自分の意思や希望よりも他人の意見を優先してしまい、選択に迷いが生じることもあるでしょう。
その結果、就職活動そのものを楽しめず、不安やストレスが増大してしまいます。
就職活動を成功させるポイント

就職活動の進め方は、人によって異なります。
しかし、就職活動を成功させるポイントの中には、多くの就活生に共通していることもあります。
![]()
限られた時間の中で的確に行動することは、効率的な就職活動の実現につながるでしょう。
そこで、ここからは多くの就活生にあてはまる就職活動を成功させるポイントを就職活動の各段階にわけて紹介します。
これから就職活動を始めようとしている方や就職活動でお悩みの方は、参考にしてください。
インターンシップ
インターンシップとは、学生が在学中に企業や団体で就業体験できる制度のことです。
実際の仕事や職場の雰囲気を知ることで、業界や職種への理解を深め、自分に合ったキャリアを考えるきっかけになります。
インターンシップにはいくつかの種類があり、目的や期間、内容によって分類されます。
主なインターンシップの種類は、以下のとおりです。
主なインターンシップの種類
- 短期インターンシップ:期間が1日~1週間程度で会社説明やグループワーク、社員交流が中心
- 長期インターンシップ:期間が数か月~1年以上で実際の業務に近い形でプロジェクトや仕事を担当
- 就業型インターンシップ:期間が数週間~数か月で社員と一緒に実務をこなすことで実際の働き方や会社の雰囲気を理解する
- オンラインインターンシップ:期間が1日~数週間でWeb会議システムを用いたワークや説明会、オンライン課題がメイン
- 海外インターンシップ:期間が数週間~数か月で現地企業での実務や研修を経験
インターンシップの中には、採用選考に直結するものもあります。
そのため、以下のようなことを意識しながら参加しましょう。
就活生がインターンシップを成功させるためのポイント
- 目標を明確にする
- 事前に参加する企業や業界の情報を取得する
- 自己紹介や志望動機などを簡潔に伝えられるようにする
- 積極的な姿勢をアピールする
- 社員や参加者と交流する
- メモを取って定期的に振り返る
- 時間や礼儀を守る
- フィードバックを素直に受け止める
インターンシップについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
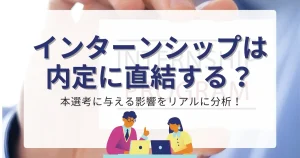
自己分析
自己分析とは、自分の強み・弱み、価値観、興味関心、経験などを整理して理解するプロセスのことです。
就職活動においては、自分を深く知ることで以下のようなことを明確にできます。
自己分析により明確になること
- 得意なこと・苦手なこと
- 仕事において重視すること
- 興味・関心の方向性
- 過去の経験から得た学び
- キャリアプランの方向性
自己分析を成功させるためには、以下のようなことを意識してみましょう。
自己分析を成功させるためのポイント
- 「企業選びの軸を決めたい」、「自己PRを作りたい」などゴールを意識して進める
- 学業・アルバイト・部活動・ボランティアなどを時系列で書き出す
- 成功体験だけでなく、困難をどう乗り越えたかを振り返る
- 具体的な成果や学びに注目する
- 友人・家族・先輩に自分の強みを聞く
- 適性診断・性格診断を参考にして自己理解を補強する
- 定期的に自己分析する
効率よく自己分析を進めたい方は、こちらの記事をご覧ください。
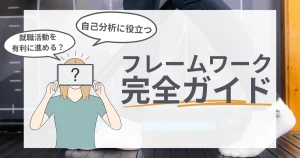
業界・企業研究
業界・企業研究とは、就職活動において志望する業界や特定の企業について情報を集め、理解を深めることです。
「どんな業界が自分に合うのか」、「その企業はどんな特徴を持っているのか」を明確にすることで、ミスマッチを防ぎます。
業界・企業研究では、以下のような情報源を活用します。
業界研究の主な情報源
- 業界地図・就職四季報
- 新聞・経済誌
- 業界団体・協会のHP
- 就職サイトの業界特集ページ
企業研究の主な情報源
- 企業の公式HP
- 有価証券報告書・IR資料
- 就職四季報(企業版)
- OB・OG訪問
- 口コミサイト
- ニュースサイト・プレスリリース
また、業界・企業研究で集める主な情報は、以下のとおりです。
業界研究で集める情報の具体例
- 業界全体の規模(市場規模、売上高など)
- 成長性(将来性のある分野か、縮小傾向か)
- 業界の主要企業(シェア上位やリーディングカンパニー)
- 業界内のビジネスモデル(収益の仕組み、提供価値)
- 業界全体の課題やトレンド(人材不足、IT化、国際競争など)
- 働き方の傾向(労働時間、勤務地、給与水準)
企業研究で集める情報の具体例
- 基本情報(設立年、従業員数、売上高、拠点など)
- 事業内容(主力製品・サービス、事業分野ごとの特徴)
- 経営理念・ビジョン(社長のメッセージや企業が大切にしている価値観)
- 強み・弱み(競合との差別化ポイント、自社の課題)
- 財務状況(売上・利益の推移、安定性や成長性)
- 社風・企業文化(社員の声、働き方、研修制度)
- 採用情報(求める人物像、募集職種、選考フロー)
- 競合企業との比較(事業領域や市場での立ち位置)
業界・企業研究を成功させるためには、以下のようなことを意識しましょう。
業界研究を成功させるポイント
- 業界全体の把握から始める
- 複数業界を比較する
- 数字やデータで理解する
- 業界の将来像を考える
- 情報源を使い分ける
企業研究を成功させるポイント
- 競合企業と比較する
- 社員の声を直接聞く
- 自分の価値観と照らし合わせる
業界分析のコツについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

応募書類の準備
就職活動では、各企業の新卒採用にエントリーしたり、書類選考を受けたりするために応募書類を作成しなければなりません。
主な応募書類は、「履歴書」と「エントリーシート(ES)」の2つです。
2つの書類には、以下のような項目が設けられています。
履歴書の主な項目
- 氏名・フリガナ
- 生年月日
- 性別
- 住所・連絡先
- 学歴
- 資格・免許
- 志望動機
- 自己PR
- 通勤希望
- 本人希望欄
エントリーシート(ES)の主な項目
- 基本情報(氏名・生年月日・住所・連絡先など)
- 学歴
- 志望動機
- 自己PR
- 学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)
- 資格・スキル
- キャリアプラン
- 自己分析・価値観に関する設問
応募書類を準備するときは、以下のようなことを意識してください。
応募書類を準備するときに意識すべきポイント
- 自誤字脱字や記入漏れがないようにする
- 手書きの場合は丁寧に書く
- PC作成の場合はレイアウトやフォントを整える
- 数字や状況を使い、自分の成果や学びを客観的に示す
- 志望動機や自己PRは、その企業に合わせて内容を変える
- 履歴書・エントリーシート・面接で話す内容が矛盾しないようにする
- 期間に余裕を持って作成する
- 第三者にチェックしてもらう
履歴書について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
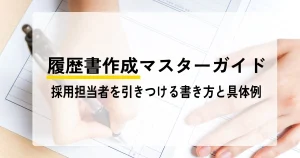
筆記試験・適性検査
筆記試験・適性検査とは、企業が応募者の基礎学力や思考力、性格などを把握するために実施する選考方法です。
面接前の足切りや、面接だけでは判断しにくい能力を客観的に評価する目的があります。
筆記試験・適性検査は、目的や形式によって以下のように分類されます。
筆記試験の主な種類
- 一般常識試験
- 学力試験(国語・数学・英語など)
- 論理・判断力試験
適性検査の種類
- 性格検査(パーソナリティテスト)
- 能力検査(能力適性テスト)
- Web適性検査(SPI3、玉手箱、CAB、TG-WEBなど)
適性検査の一種であるWeb適性検査について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

筆記試験・適性検査を成功させるためには、以下のようなことを意識しましょう。
筆記試験を成功させるポイント
- 出題範囲を把握する
- 基礎力を固める
- 過去問や模擬問題で練習する
- 時間管理を意識する
適性検査を成功させるポイント
- 設問に対して迷わず回答する
- 繰り返し練習し、計算力や論理問題のスピードと正確性を高める
- 途中で通信が中断しないようにする
グループディスカッション
グループディスカッション(GD)とは、複数の応募者がグループを作り、与えられたテーマについて議論する選考方法です。
単に議論の結論だけでなく、コミュニケーション能力や協調性、リーダーシップ、論理的思考力などを評価する目的で実施します。
グループディスカッションは、テーマや形式によって以下のように分類されます。
グループディスカッション(GD)の主な種類
- テーマ型ディスカッション:社会問題や時事問題などのテーマについて自由に議論
- ケース型ディスカッション:企業が直面する課題やビジネスケースをもとに議論
- 役割分担型ディスカッション:参加者に役割(司会、書記、分析担当など)が割り当てられ、役割に沿って議論
- ディベート型(賛否討論型):賛成・反対の立場にわかれて議論
- ブレインストーミング型:量を重視して多くのアイデアを出し最後にまとめる
グループディスカッションを成功させるためには、以下のようなことを意識しましょう。
グループディスカッション(GD)を成功させるポイント
- 積極的に発言する
- 他人の意見を尊重する
- 論理的に意見をまとめる
- 事前に練習する
- テーマに関連する知識を持っておく
- 冷静に考えながら発言する
面接
面接は、新卒採用において重要な選考プロセスのひとつです。
性格や協調性、コミュニケーション能力など、書類だけではわからない応募者の特性を把握したり、選考を受けている企業への志望度を見極めたりします。
面接は、選考ステージや目的などによって以下のように分類されます。
面接の主な種類
- 個人面接:面接官1人が応募者1人に対して実施する面接
- 集団面接(グループ面接):複数の応募者が同時に面接を受ける
- 役員面接(最終面接):企業の役員や経営層が面接官を担当する面接
- Web面接・オンライン面接:ZoomやTeamsなどのオンラインツールを使った面接
面接を成功させるためには、以下のようなことを意識しましょう。
面接を成功させるためのポイント
- スーツは清潔感のある着こなし、髪型・爪・靴も整える
- 明るくハキハキした挨拶、敬語を正しく使う
- 背筋を伸ばして座り、笑顔や適度なアイコンタクトを意識する
- 強みや経験を具体的なエピソードをそえて伝える
- なぜその企業で働きたいのかを他社との差別化も含めて説明する
- 事業内容や社風を踏まえた質問や回答で熱意を伝える
- 結論→理由→具体例の順で話す
- 長すぎず簡潔に、質問に対して的確に答える
面接のコツについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
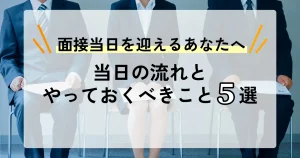

ーまとめー
就職活動の悩みはひとりで抱え込まないようにしよう!

今回は、就活生が抱える悩みをランキング形式で紹介しました。
就職活動は、不安や悩みがつきものです。
そのような中で、解決策を把握し、適切に行動することで就職活動を前向きに進められます。
就職活動の成功において重要なのは「自分だけが悩んでいるのではない」と知り、一人で抱え込まず、支援サービスや周囲の人を頼ることです。
そんな就活生の強い味方となるのが、新卒採用に特化した求人サイト「リクスタ」です。
リクスタは、就職活動の支援実績が豊富なアドバイザーが就活生をサポートしてくれるため、就活生の悩みを的確に解決してくれます。
また、入念なヒアリングを通じて就活生ごとに適した求人情報を提供してくれるため、質の高い就職活動が期待できます。
興味がある方は、ぜひ利用してみてください。
また、転職活動向けのサービスをお探しの方は、以下の求人サイトも検討してみてください。
![]()
まとめ
就職活動の悩みはひとりで抱え込まないようにしよう!

今回は、就活生が抱える悩みをランキング形式で紹介しました。
就職活動は、不安や悩みがつきものです。
そのような中で、解決策を把握し、適切に行動することで就職活動を前向きに進められます。
就職活動の成功において重要なのは「自分だけが悩んでいるのではない」と知り、一人で抱え込まず、支援サービスや周囲の人を頼ることです。
そんな就活生の強い味方となるのが、新卒採用に特化した求人サイト「リクスタ」です。
リクスタは、就職活動の支援実績が豊富なアドバイザーが就活生をサポートしてくれるため、就活生の悩みを的確に解決してくれます。
また、入念なヒアリングを通じて就活生ごとに適した求人情報を提供してくれるため、質の高い就職活動が期待できます。
興味がある方は、ぜひ利用してみてください。
また、転職活動向けのサービスをお探しの方は、以下の求人サイトも検討してみてください。
![]()
-1024x341.webp)
\ 新卒求人サイト /
.webp)
\ 新卒求人サイト /
-1024x341.webp)
\ 飲食業界求人サイト/
-.webp)
\飲食業界求人サイト/

\ 整備士求人サイト /
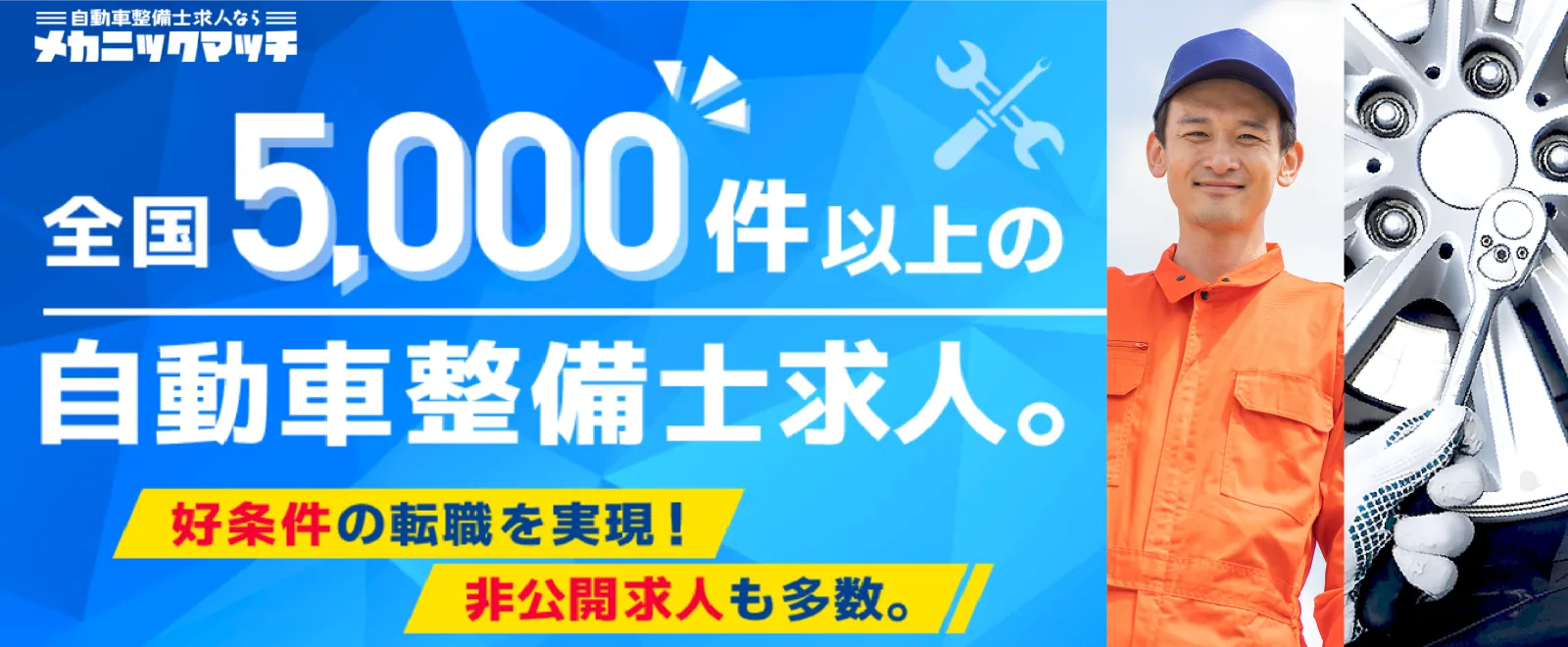
\ 整備士求人サイト /

\ 寿司職人求人サイト /

\ 寿司職人求人サイト /