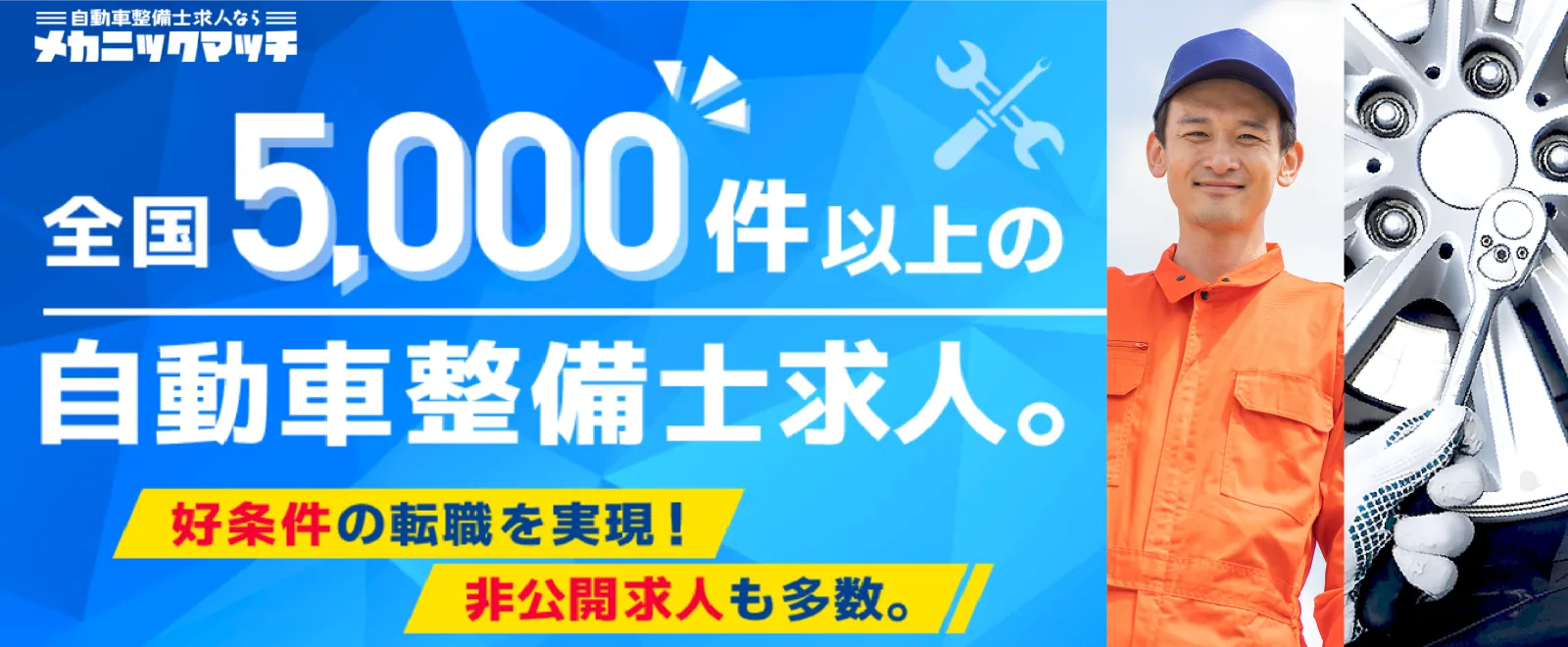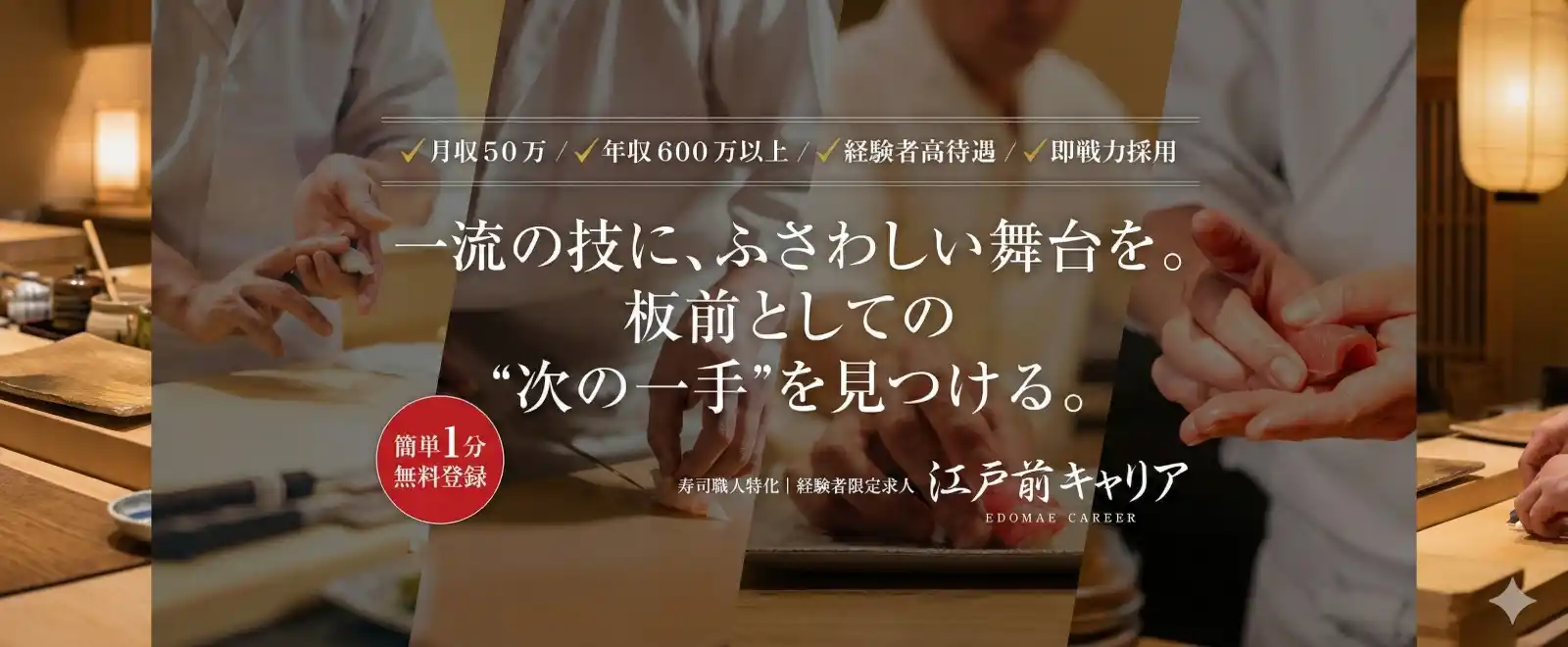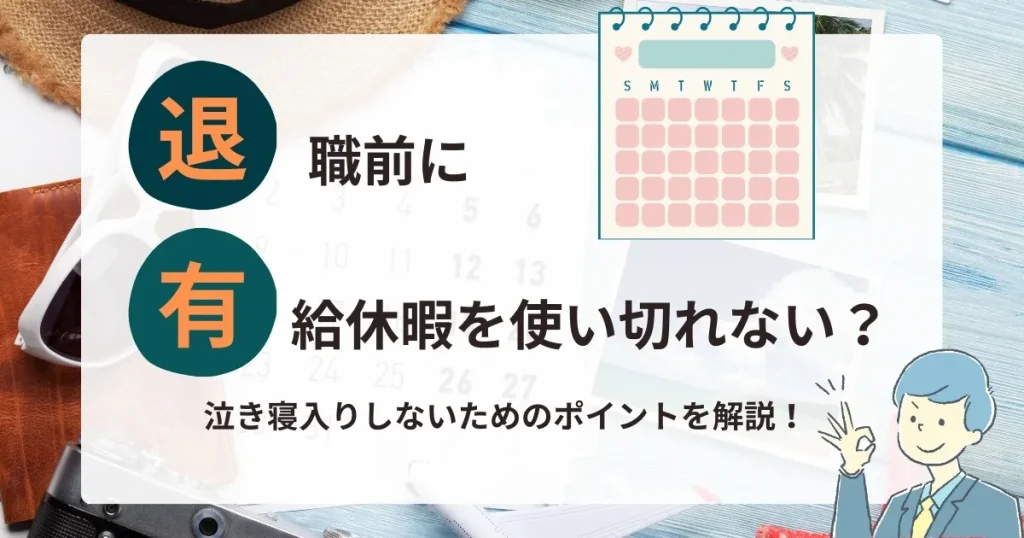
退職関連の悩みとしてよく見られるのが、有給休暇についてです。
とくに、勤続年数が長く、有給がたくさん残っていたり、業務の引き継ぎ等で忙しくなったりすると、有給休暇を使いきれないという事態に陥りかねません。
そこで、本記事では有給休暇を使いきれず、泣き寝入りしないためのポイントを紹介します。
この記事を参考に、有給休暇を使い切り、円満に退職しましょう。

労働基準法における有給休暇の基本ルール

労働基準法第39条では、有給休暇(年次有給休暇)について以下のような基本ルールが定められています。
有給休暇が付与される条件
有給休暇は以下の条件を満たす労働者に付与されます。
有給休暇が付与される条件
- 雇い入れから6か月が経過している
- 全労働日80%出勤している
これらの条件を満たすと、年間10日間の有給休暇が付与されます。
また、有給は勤続年数に応じて付与日数が増え、最大20日付与されます。
通常労働者の付与日数
| 継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
| 付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
| 週所定労働日数(日) | 1年間の所定労働日数(日) | 継続勤務年数(年) | |||||||
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
| 付 与 日 数 (日) | 4 | 169~216 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 3 | 121~168 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | 73~120 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
| 1 | 48~72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
有給休暇の時効
有給休暇の時効は、取得可能になってから2年間です。
したがって、有給休暇を取得せずにそのままにしておくと、2年が経過した時点で権利が消滅してしまいます。
また、会社が有給取得を妨害した場合でも、時効は進行するため、労働者自身が積極的に取得する必要がある。
なお、退職日を過ぎると権利は失効するため、注意しましょう。
企業側の義務と労働者の権利
有給休暇は、労働者の正当な権利です。
そのため、基本的に企業は有給休暇の取得を拒否することはできません。
労働者は、希望する日に有給を申請でき、会社は原則として労働者の申請を認めなければならないとされています。
なお、業務の正常な運営に支障がある場合、企業は「時季変更権」を行使し、別の日への変更を求められます。
しかし、有給取得そのものを妨げることは許されないので注意しましょう。
さらに、2019年の法改正により、企業は年5日以上の有給休暇を従業員に取得させる義務を負うようになりました。
有給休暇を使い切れない主な理由【5つ】

![]()
労務SEARCHによると、現職における有給休暇の取得しやすさについて、「どちらかといえば取得しにくい」や「取得しにくい」と回答した人の割合は、24.6%でした。
有給休暇にかんする法律が整備されつつある現代でも、有給休暇の消化に対して悩んでいる方がいます。
ここからは、有給休暇を使いきれない主な理由を5つ紹介します。
人手不足
人手が不足している職場では、退職時に有給休暇を取得しづらい状況が生じやすくなります。
とくに、代わりの人員を確保できない場合は、会社側が有給取得を事実上拒むこともあるでしょう。
本来、有給休暇は労働者の権利であり、退職前に消化できます。
しかし、周囲への配慮や職場の雰囲気から、取得を諦める人も少なくありません。
引き継ぐことが多い
退職時に引き継ぐ業務が多いと、有給休暇の取得が難しくなることがあります。
とくに、担当業務が複雑でマニュアル化されていない場合は、後任者への説明や資料作成に時間を取られ、休む余裕がなくなることもあります。
また、引き継ぎの遅れが業務に支障をきたすことを懸念し、自ら有給取得を控える人も少なくありません。
その結果、有給休暇を消化できずに退職してしまいます。
有給休暇を取得しにくい職場環境
有給休暇を取得しにくい職場環境も有給休暇を使いきれない要因のひとつです。
一例として、上司や同僚が有給取得に否定的だったり、過去に有給を消化できなかった前例があったりすると、退職時でも有給休暇の取得を遠慮してしまうことがあります。
また、会社側が暗黙のプレッシャーをかけることで、有給休暇の申請を諦めることもあります。
その結果、本来の権利を行使できずに退職を迎えてしまう人も少なくありません。
最終出社日と退職日の調整がうまくいかない
最終出社日と退職日の調整がうまくいかないと、有給休暇を消化できないことがあります。
本来、有給休暇を取得して退職日までの期間を調整することは可能です。
しかし、会社側が最終出社日を退職日と同じ日に設定したり、業務の都合で有給の取得を制限したりする場合があります。
また、労働者自身がスケジュール調整を誤り、結果的に有給を使いきれないこともあります。
有給休暇の買い取り制度がない
有給休暇の買い取り制度とは、未消化の有給休暇を企業が金銭で補償する制度です。
労働基準法では認められていませんが、一部企業では、有給休暇の買い取り制度を導入しています。
有給休暇の買い取り制度がない企業では、退職時に未消化の有給を金銭的に補填できず、結果的に使いきれないことがあります。
そのため、業務の引き継ぎや職場環境の影響で有給取得が難しい場合、休めなかった分の補償がなく、損をしてしまう事例が発生してしまうのです。
有給休暇を使い切れず泣き寝入りしないためのポイント【5つ】

ここからは、有給休暇を使いきれず泣き寝入りしないためにやるべきことを5つ紹介します。
有給休暇の残日数を定期的に確認する
| 有給休暇を消化しきるためには、定期的に残日数をチェックしましょう。
有給休暇の残日数を定期的に確認することで、計画的に取得しやすくなります。
とくに、退職時には、残日数を把握していないと、気づかないうちに消滅してしまう恐れがあります。
また、企業側の管理ミスで正しい日数が付与されていない場合もあるため、早めに確認して修正を求めましょう。
さらに、有給休暇を計画的に申請することで、業務の引き継ぎなどにも支障をきたさずに消化できます。
早めに退職の意志を伝える
| 退職時に有給休暇を使い切るためには、早めに退職の意志を伝えましょう。
退職日が近づいてから伝えると、業務の都合を理由に有給取得が難しくなります。
その結果、使い切れずに泣き寝入りすることになりかねません。
余裕をもって伝えることで、有給取得の交渉もしやすくなります。
また、早めに退職の意志を伝えることで、上司や同僚と調整する時間が確保でき、引き継ぎをスムーズに進められます。
退職の意志を伝えるときは、以下の具体例のように感謝の気持ちを示しつつ、明確に伝えましょう。

具体例①
お忙しいところ恐れ入ります。
実は、一身上の都合により、◯月◯日をもって退職させていただきたく思っております。
これまで大変お世話になりました。
詳細についてご相談させていただければと思います。

具体例②
少しご相談したいことがございます。
実は、今後のキャリアについて考えた結果、新たな道に進む決意を固めました。
できる限り円滑に引き継ぎを進めたいと思っておりますので、ご相談の時間をいただけますでしょうか?
引き継ぎ計画を立てる
| 退職時に有給休暇を使いきる環境を整えるためにも、事前に引き継ぎ計画を立てましょう。
円満退職するためにも業務の引き継ぎは欠かせません。
そのため、引き継ぎ計画なしに急に有給取得を申し出ると、業務上の問題を理由に取得を拒まれることがあります。
引き継ぎ計画を立てることで、退職前にスムーズに業務を終え、有給休暇を取得しやすくなります。
また引き継ぎ計画を上司や同僚へ共有することで、周囲の負担を軽減し、職場との調整もスムーズに進められるでしょう。
就業規則を確認する
| 有給休暇を使い切るためには、就業規則を事前にチェックしておきましょう。
就業規則を確認することで、有給休暇の取得ルールや申請方法を正しく理解し、計画的に消化しやすくなります。
とくに、退職時の有給取得については、企業ごとにルールが異なるため、事前に確認しておかないと、対応が間違っていても気付かないことがあるでしょう。
また、会社が不当な制限を設けている場合は、正しく主張するための根拠にもなります。
労働基準監督署へ相談する
| 有給休暇の取得について企業とトラブルが生じそうな場合は、労働基準監督署へ相談しましょう。
労働基準監督署は、労働基準法に基づき労働環について監督・指導する行政機関です。
労働基準監督署へ相談することで、会社が不当な理由で有給休暇の取得を妨げている場合に適切な対応を取れます。
また、労働基準監督署は、違法な対応に対して指導したり、是正勧告したりする権限を持っているため、正当な権利を守るためにも積極的に利用しましょう。
有給休暇中に次の職場で働くことは可能か?

結論から伝えると、有給休暇中であっても次の職場で働けます。
しかし、有給休暇中に働くためには、以下の点に注意する必要があります。
競業避止義務
競業避止義務とは、従業員が在職中または退職後に、同業他社で働いたり競争関係にある事業を担うことを制限する義務のことです。
有給休暇中でも雇用関係は継続しており、現職の競業避止義務が適用されることがあります。
競業避止義務に違反すると、懲戒処分や損害賠償請求の対象になることもあります。
とくに、転職先が同業他社である場合、現職の企業から秘密保持義務違反を疑われるため注意しましょう。
有給休暇中に次の職場で働くときは、就業規則や雇用契約の内容を確認し、必要に応じて現職の会社と相談してください。
転職先の就業規則
| 有給休暇中に次の職場で働く場合、転職先の就業規則に違反していないかチェックしましょう。
一部の企業では、正式な入社日以前の業務従事を禁止していることがあります。
とくに、金融業界や公務員・官公庁関係など、コンプライアンスへの意識が高い業界では、正式な入社日以前の業務従事を禁止している傾向が強いため注意しましょう。
また、雇用契約が未締結の状態で働くと、労働条件のトラブルにつながる恐れがあります。
さらに、転職先の労働時間管理や社会保険の適用条件にも影響を与えるため、事前に就業規則を確認し、適切に手続きを進めてください。
社会保険・雇用保険の手続き
| 有給休暇中に次の職場で働く際は、社会保険・雇用保険の手続きに注意しましょう。
現職の雇用関係が続いているため、社会保険や雇用保険の加入も継続されます。
しかし、転職先で新たに社会保険に加入すると二重加入となり、手続きに不備が生じることがあります。
また、雇用保険の失業給付にも影響が出る場合があるため、事前に転職先と現職の担当者に確認し、適切な手続きを進めましょう。
有給休暇取得でよくあるQ&A

ここからは、退職前に有給休暇を取得する際によくあるQ&Aを3つ紹介します。
退職願を提出した後でも有給休暇の申請は可能か?
退職願を提出した後でも、有給休暇は申請できます。
退職願とは、労働者が会社に対して自主的に退職したい意思を伝える書面です。
労働基準法では、有給休暇は労働者の権利として認められており、退職日までの期間であれば取得できます。
なお、退職時は会社の業務状況を考慮し、引き継ぎを円滑に進めなければなりません。
そのため、会社側が業務に大きな支障をきたすと判断した場合、一部の日程変更を求められることもあります。
しかし、引き継ぎが残っていても有給休暇は取得できます。
退職日直前にまとめて有給休暇を取得するのは可能か?
退職日直前にまとめて有給休暇を取得することは可能です。
労働基準法により、有給休暇は労働者の正当な権利とされており、退職日までであれば取得できます。
また、会社側が業務に支障をきたす場合でも、取得自体を拒否することはできません。
なお、業務の引き継ぎや調整を円滑に進めるためには、早めに有給休暇を申請し、上司や人事と事前に相談しておきましょう。
パートやアルバイトでも有給休暇を取得できるのか?
パートやアルバイトも正社員と同様に有給休暇が付与されます。
なお、有給休暇を取得するためには、労働基準法第39条で定められている、週の所定労働日数や勤続期間の条件を満たす必要があります。
一例として、週3日以上勤務し、雇用開始から6ヶ月間継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上であれば、有給休暇の取得が認められます。
有給休暇中にやるべきこと【3つ】

有給休暇を計画的に使用する人もいれば、退職前にまとめて取得する人もいるでしょう。
有給休暇中に次の職場で働かない場合は、時間に余裕ができるため、さまざまなことに取り組めます。
ここからは、有給休暇中にやるべきことを3つ紹介します。

スキルアップする
| 転職先でさらなるキャリアアップを目指す方は、有給休暇中にスキルアップしましょう。
退職前の有給休暇中にスキルアップすることで、転職先での即戦力としての評価を高められます。
また、新たな環境への適応力を強化することで、キャリアの選択肢を広げられるでしょう。
有給休暇中は時間に余裕があるため、学習や資格取得に集中しやすいため、ぜひスキルアップしてみてください。

リフレッシュする
| 転職後に高いパフォーマンスを発揮するために、有給休暇中にリフレッシュしましょう。
退職前の有給休暇中にリフレッシュすることで、心身の疲れを癒し、新しい職場でのスタートをより良い状態で迎えられます。
また、リラックスすることで、前向きな気持ちになり、次の仕事へのモチベーションも高まります。
十分な休息を取ることで健康を維持し、新たな環境へスムーズに適応しましょう。

転職活動を進める
| 退職してから転職活動を始める方は、有給休暇中に転職活動を進めましょう。
退職前の有給休暇中に転職活動を進めることで、時間的な余裕を持って企業研究や面接準備を進められます。
また、在職中の忙しさから解放され、冷静にキャリアを見直す機会にもなります。
働きながら転職活動を進めたい方は、こちらの記事をご覧ください。
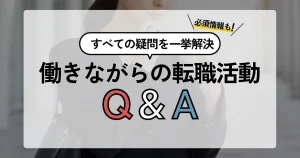
有給休暇取得以外にやるべきこと【6つ】

退職時は、有給休暇の取得や業務の引き継ぎ以外にもやるべきことがあります。
ここからは、退職を決意してから退職するまでにやるべきことを6つ紹介します。
退職願や退職届を提出する
退職時には、会社の規定に従って退職願や退職届を提出しなければなりません。
退職願は「退職したい」という意思を示すもので、会社が受理しない限り撤回できます。
一方、退職届は正式な退職の意思表示であり、提出後の撤回は難しくなります。
会社によって必要書類が異なるため、就業規則を確認し、適切なタイミングで提出しましょう。
退職願や退職届について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
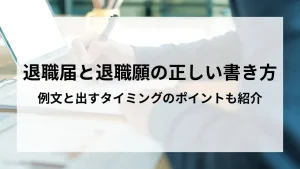
取引先や関係者へ挨拶する
| 退職時には、取引先や関係者へ挨拶しましょう。
これまでの感謝を伝えることで、円満な関係を維持できるだけでなく、今後のキャリアにもいい影響を与えます。
とくに、同じ業界で働く場合は、将来的に再び関わることもあるため、礼儀を欠かさないようにしましょう。
対面で挨拶するのが望ましいですが、難しい場合は電話やメールで挨拶してください。
退職時の挨拶についてお悩みの方は、こちらの記事をご覧ください。
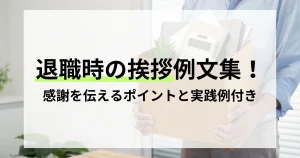
会社からの貸与物を返却する
退職時には、会社から貸与された物をすべて返却しなければなりません。
代表的な貸与物として、社員証や制服、PC、スマートフォン、鍵、書類などがあります。
返却漏れがあると、トラブルの原因となるため、会社の指示に従い、退職日までに速やかに返却しましょう。
また、データの取り扱いにも注意し、私物との混在がないかも確認してください。
お菓子を渡す
| 退職するときは、感謝の気持ちを伝えるためにお菓子を渡しましょう。
とくに、お世話になった上司や同僚へ、手軽に分けられる個包装のお菓子を選ぶと喜ばれます。
なお、職場の文化や規模によっては不要な場合もあるため、周囲の慣習を確認しましょう。
また、無理に高価なお菓子を用意する必要はありません。
「お世話になりました」などの一言を添えたメッセージカードとともに渡してください。
退職時に渡すお菓子についてお困りの方は、こちらの記事をご覧ください。

必要書類を受け取る
| 退職時には、会社から必要書類を受け取りましょう。
主な書類には、以下のようなものがあります。
退職時に企業から受け取る書類
- 離職票
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 退職証明書
- 健康保険資格喪失証明書
上記のような書類は、転職先での手続きや失業保険の申請に必要となるため、退職前に会社へ確認し、確実に受け取りましょう。
万が一、受け取れなかった場合は、速やかに会社へ問い合わせてください。
公的手続きを進める
| 退職時は、公的手続きを速やかに進めましょう。
退職時にやるべき公的手続きとして、健康保険や年金、雇用保険、税金などがあります。
人によって必要な手続きが異なるため、転職先の有無や自身の状況に応じて進めましょう。
退職時に転職先が決まっていると、新しい会社が手続きを進めてくれますが、未定の場合は自分で国民健康保険や国民年金への切り替え、失業保険を申請しなければなりません。
期限や手続き方法などを確認し、早めの対応を心掛けましょう。

ーまとめー
計画的に有給休暇を使い切ろう!

今回は、有給休暇を使いきれず、泣き寝入りしないためのポイントを紹介しました。
有給休暇は労働者の正当な権利です。
また、有給休暇を使うことは、心身を休めるだけでなく、転職活動や引っ越しなどの準備を進めるためにも役立ちます。
未消化のまま退職すると失効してしまうため、計画的に取得しましょう。
![]()
まとめ
計画的に有給休暇を使い切ろう!

今回は、有給休暇を使いきれず、泣き寝入りしないためのポイントを紹介しました。
有給休暇は労働者の正当な権利です。
また、有給休暇を使うことは、心身を休めるだけでなく、転職活動や引っ越しなどの準備を進めるためにも役立ちます。
未消化のまま退職すると失効してしまうため、計画的に取得しましょう。
![]()

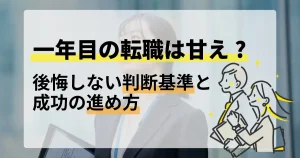

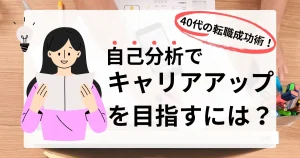


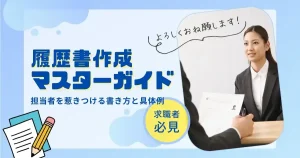

-.webp)