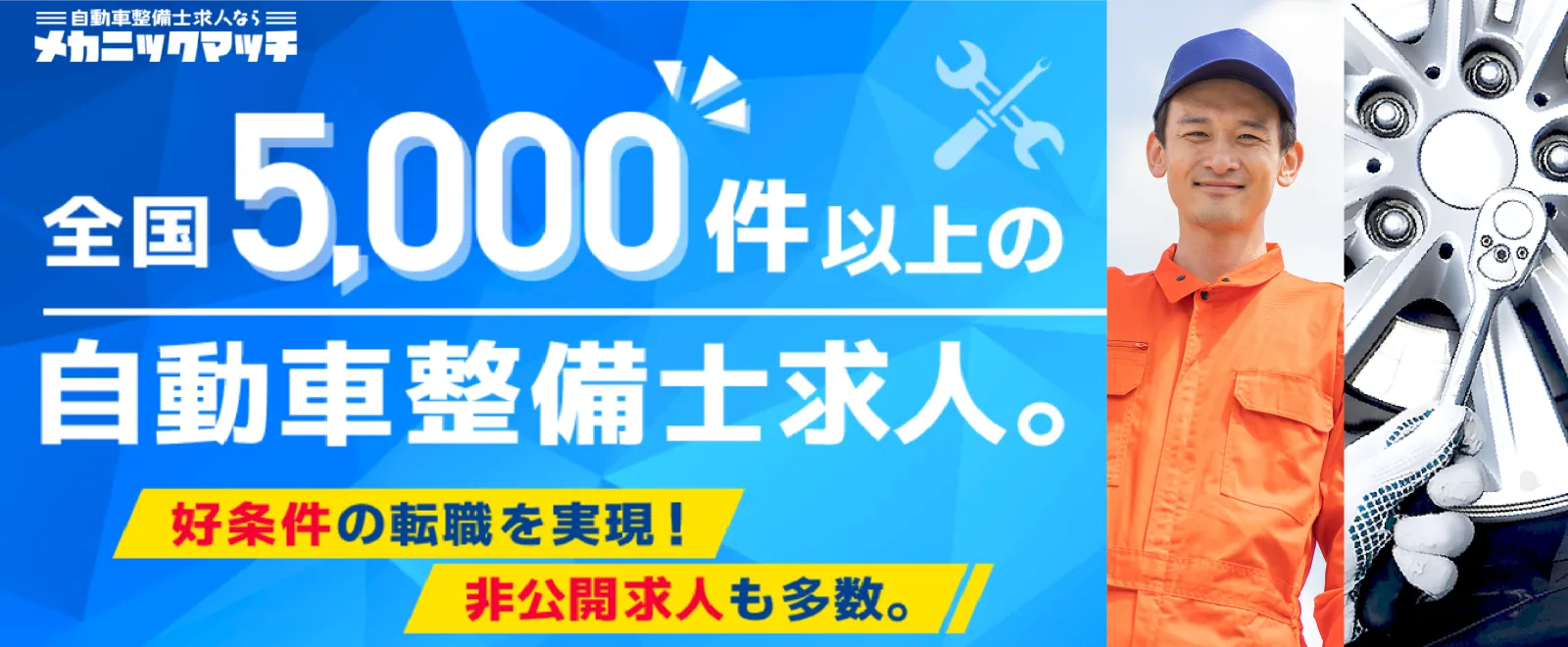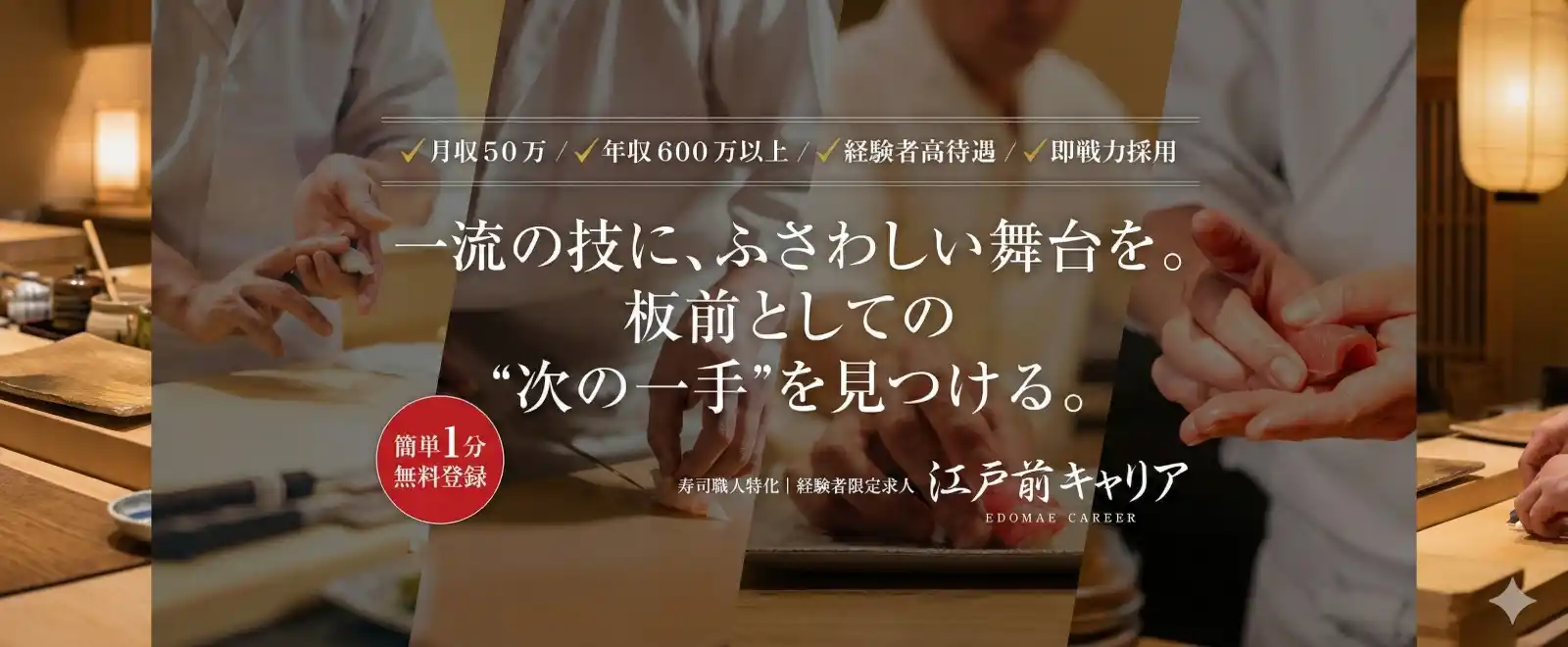転職活動を始めようとすると、最初に直面するのが「自己分析」です。
履歴書や職務経歴書、面接の場などで自分の「強み」と「弱み」を整理して伝えることは欠かせません。
しかし、多くの人が

強みは思いつくけど、弱みがわからない。



そもそも弱みなんて言いたくない。
と感じています。
とくに、前向きにキャリアを積んできた人ほど、あえて自分の短所を掘り下げることに抵抗があります。
しかし、実は「弱みを言えない」ことは、転職活動において大きなハンデです。
この記事を参考に、自分の弱みへの理解を深め、「魅力的に伝えられる武器」へと変化させましょう。


中途採用で「弱み」を聞かれるのはなぜか?


応募者の「弱み」を通じて企業が見極めたいことは、短所そのものではありません。
中途採用で「あなたの弱みを教えてください」と聞かれるのには、明確な意図があります。
ここからは、中途採用で「弱み」を聞かれる理由を3つ紹介します。
どのくらい自己理解を深めているか見極める
中途採用の面接で「弱み」を聞かれる理由のひとつは、自己理解の深さを見極めるためです。
ビジネスでは、さまざまな失敗やトラブルがともないます。
そのなかで、損失を最小限に抑えるためには、状況を正確に把握し、適切に対処しなければなりません。
自分の弱みを正しく理解している人は、成長に向けた行動を起こせます。
また、自己分析ができる人は再現性のある成果を出しやすく、信頼性の高い人材と評価されます。
このように、企業は社会人経験を積んだ人が自分の課題をどれだけ客観的に把握しているかを重視します。
「改善力」や「学習意欲」を見極める
応募者の改善力や学習意欲を確かめることも中途採用の面接で「弱み」を聞かれる理由のひとつです。
新卒採用では、中途採用よりも「成長性」に重きをおく傾向があります。
そのため、失敗や課題に直面した際の姿勢を通じて、成長できる人かどうかを判断しています。
弱みを正直に話すだけでなく、具体的な改善の取り組みを伝えることで、採用担当者から信頼を得られるでしょう。
企業への適性を見極める
企業との適性を見極めることも中途採用の面接で「弱み」を聞かれる理由のひとつです。
採用担当者は、選考を通じて応募者の性格や行動傾向が職場環境やチーム文化に合うかを確認しています。
どんな場面で弱みが表れやすいかを知ることは、入社後の働き方を具体的にイメージすることにつながります。
また、弱みが業務に支障を与えない範囲かどうかも重要な判断材料です。
自分に合った企業を探したい方は、こちらの記事をご覧ください。
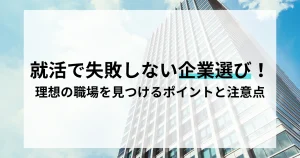
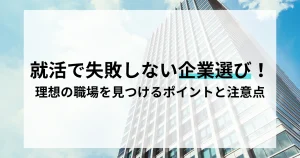
「弱みが見つからない人」の共通点【5つ】


人によっては、自分の「弱み」がわからないという方もいます。
しかし、「弱み」が見つからないことの要因は、単に自己分析不足というだけではありません。
心理的な要素や思考の癖も関係していることがあります。
ここからは、弱みが見つからない人の共通点を5つ紹介します。
完璧主義
完璧主義な人は、自分の弱みを見つけるのが苦手です。
完璧主義の人は、常に高い基準で自分を評価するため、欠点を「認めてはいけないもの」と感じることが少なくありません。
それにより、弱みを探そうとしても「まだ足りない部分を挙げるのは恥ずかしい」と思ってしまいます。
「強み」と「弱み」を別々に考えている
「強み」と「弱み」を別々に考えている人は、自分の弱みを見つけることが苦手です。
強みと弱みは、本来ひとつの性質の裏表であり、切り離せるものではありません。
一例として、「慎重さ」は強みでもあり、「行動が遅くなる」という弱みにもつながります。
この関係性を理解できないと、短所を単なる欠点として捉えてしまいます。
自分のことを客観視できない
自分のことを客観視できない人は、自分の弱みを見つけるのが苦手です。
主観的な視点だけで考えると、行動の癖や課題に気づきにくくなります。
それにより、同じ失敗を繰り返しても原因を分析できず、成長の機会を逃してしまうことも少なくありません。
客観的に自分を振り返ることで、弱みの傾向や改善すべき点が明確になります。
他人の意見を素直に受け入れられない
他人の意見を素直に受け入れられない人は、自分の弱みを見つけるのが苦手です。
自分の考えに固執してしまうと、他者からの指摘を成長のヒントとして捉えにくくなります。
それにより、改善点を見逃し、同じ課題を抱え続けてしまうでしょう。
他人の意見は、自己理解を深めるための貴重な材料になります。
弱みを探すときは、周囲の声に耳を傾け、自分では気づけない弱みを受け入れましょう。
弱みがあることが悪いことであると考えている
弱みがあることを悪いことだと考えている人は、自分の弱みを見つけるのが苦手です。
短所を「欠点」や「評価を下げる要素」と捉えてしまい、直視することを避けてしまう方も少なくないでしょう。
しかし、弱みは成長の余地を示すサインでもあり、改善の方向性を教えてくれる存在です。
弱みを受け入れることで、自己理解が深まり、より現実的な目標を設定できます。
自己分析で弱みを掘り起こす流れ


自分の弱みは、順序立てて進めることで効率よく見つけられます。
ここからは、自己分析で弱みを掘り起こす流れを4つのステップにわけて紹介します。
過去の経験を振り返る
| 弱みを探すためには、まず過去の経験を振り返りましょう。
一例として、以下のように箇条書きで記載してください。
過去の経験の具体例
- 丁寧にしすぎて納期がギリギリになった
- 考えをまとめるのに時間がかかり、会議で自分の意見を伝えられなかった
- 相手に合わせすぎて疲れる
- 営業ノルマを達成できなかった
- 同時に複数案件を進めるとミスが多くなってしまう
弱みは抽象的に考えるよりも、実際に困った場面や失敗した体験の中に表れます。
![]()
![]()
自分の行動や感情を具体的に思い出すことで、どんな状況で苦手が出やすいかが明確になるでしょう。
また、過去を振り返る過程で、自分の成長や努力の跡にも気づけます。
フレームワークを使いながら過去の経験を振り返りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
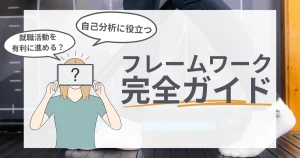
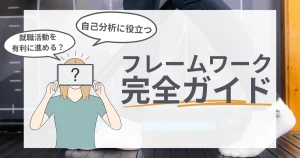
自分の経験をカテゴライズする
| 弱みを探すためには、自分の経験をカテゴライズしましょう。
一例として、以下のようなカテゴリーに分類してみてください。
自分の弱みを整理するカテゴリーの具体例
- 思考タイプ(考え方・判断の癖)
- 行動タイプ(実行力・タスク処理の癖)
- 対人タイプ(人との関わり方の癖)
- 感情タイプ(心の動き・メンタル面の癖)
- スキル・能力タイプ(実務面の課題)
- 環境・適応タイプ(働く環境との相性)
経験を分類・整理すると、状況ごとの行動パターンを把握しやすくなります。
また、経験を整理することで、自分がどんな環境で力を発揮しにくいかを分析できます。
弱みを言語化する
| 弱みを探すためには、弱みを言語化しましょう。
一例として、以下のように言語化してみてください。
弱みの言語化の具体例
- 行動し始めるのが遅い⇒入念に計画を立ててしまい行動が遅れる
- 対人関係にストレスを感じやすい⇒相手に気を使いすぎて疲れる
- 心配性⇒自信が持てず慎重になりすぎる
- 失敗を引きずりやすい⇒責任感が強く完璧主義
- 承認欲求が高い⇒評価に敏感で落ち込みやすい
言語化することで、頭の中でぼんやりと感じている苦手意識を、言葉にすることで具体的な課題として捉えられるようになります。
また、言葉にすることで改善策を考えやすくなり、前向きな自己理解につながります。
他人からフィードバックをもらう
| 弱みを探すためには、他人からフィードバックをもらいましょう。
自分では気づかない癖や行動傾向は、他者の視点から見て初めて明らかになることがあります。
身近で信頼できる上司や同僚、友人などに意見を聞くことで、客観的な弱点を把握できるでしょう。
また、他人の指摘を受け入れる姿勢は、成長意欲の表れとしてプラスに評価されます。
このように、他人の声を自己理解の材料として活かすことで、より実践的で深い自己分析が実現できます。
転職や就職のプロから自己分析結果に対するフィードバックをもらいたい方は、こちらのサービスもご利用ください。
-1024x341.webp)
-1024x341.webp)
\ 新卒求人サイト /
.webp)
.webp)
\ 新卒求人サイト /


\ 生鮮業界求人サイト /


\生鮮業界求人サイト/


\ 整備士求人サイト /
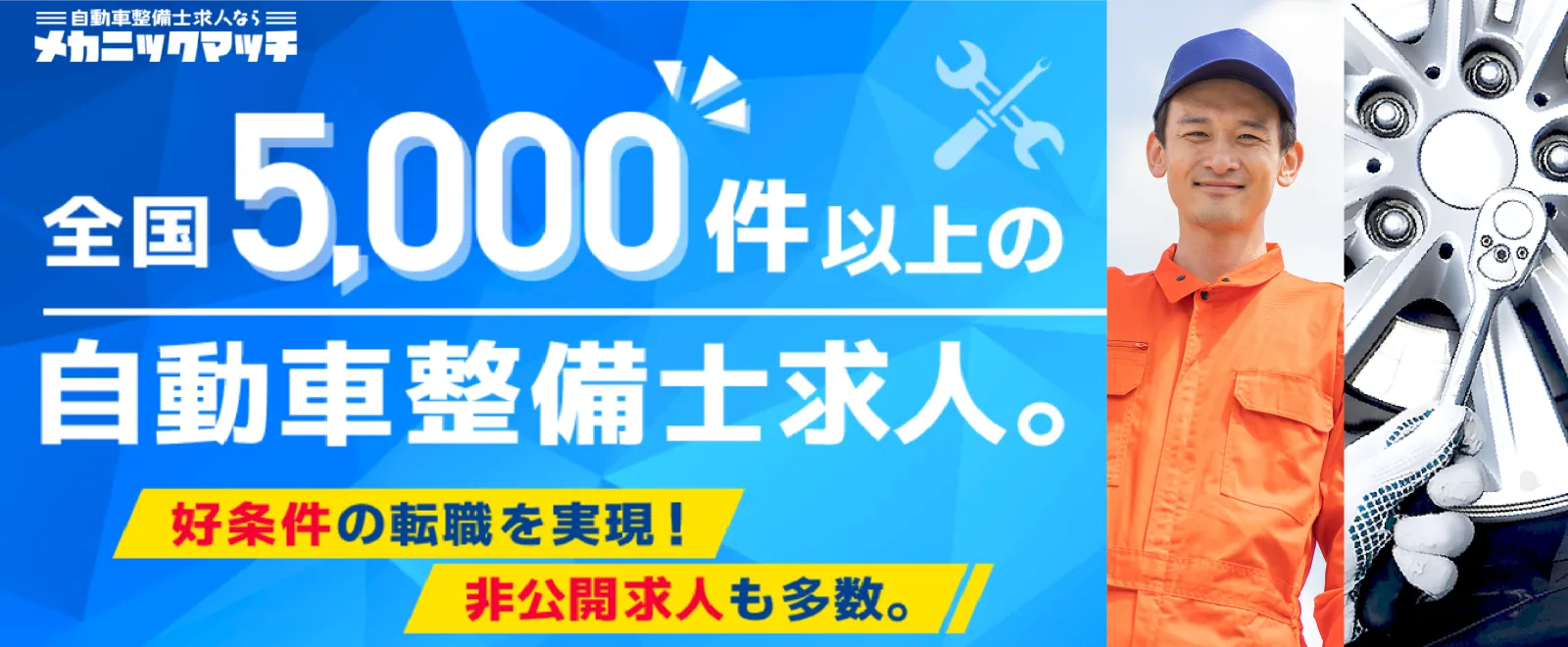
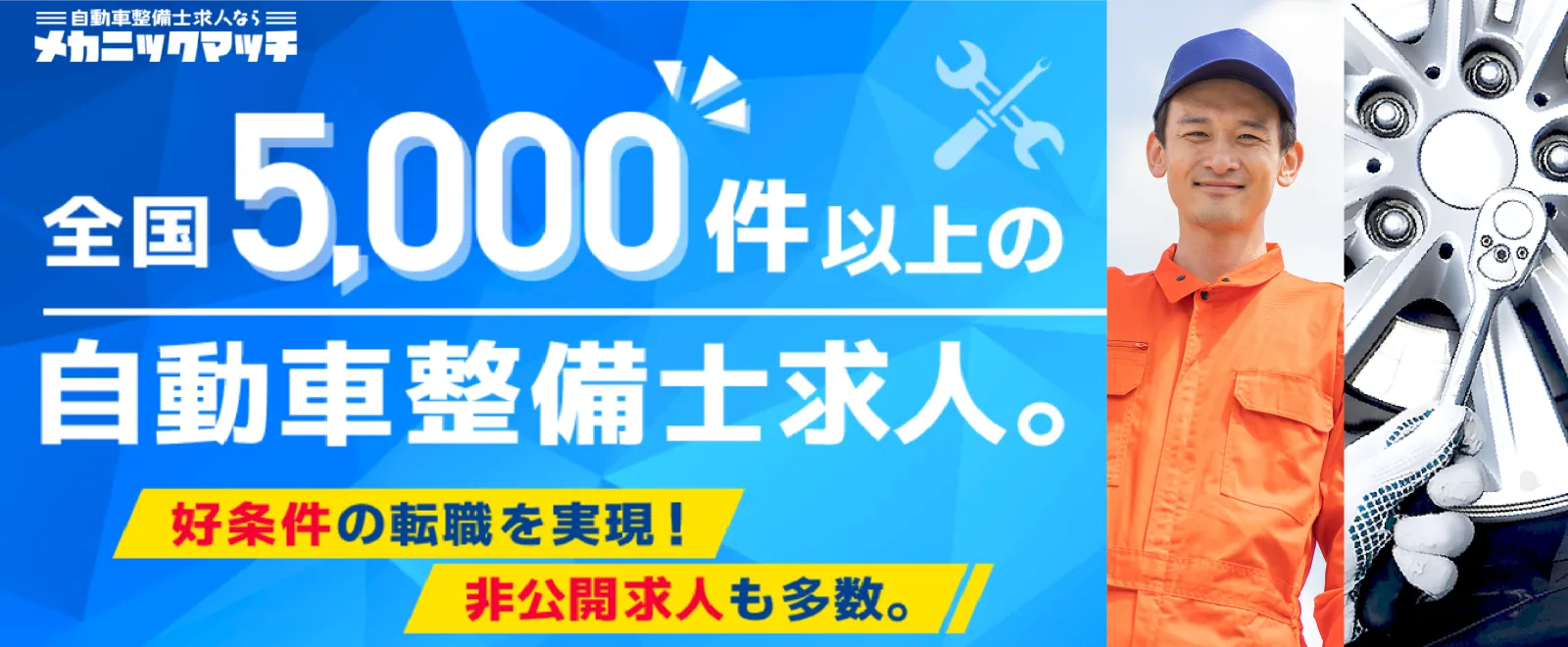
\ 整備士求人サイト /


\ 寿司職人求人サイト /


\ 寿司職人求人サイト /
弱みを伝えるときの例文【8選】


転職活動で重要なことは、「弱み」を見つけることではありません。
自己分析によって見つけた「弱み」を採用担当者の印象に残るようにアピールすることが求められます。
応募書類や面接で「弱み」をアピールする場合は、以下のようなことを意識する必要があります。
応募書類や面接で「弱み」をアピールするときに意識すべきこと
- 「強み」と一貫性を持たせる
- 応募企業・職種に関係のない「弱み」を選ぶ
- 「改善の工夫」まで語る
- コンパクトにまとめる
ここからは、上記のポイントをおさえた「弱み」の例文を8つの「弱み」をもとに紹介します。
せっかち


具体例①
私は、少し“せっかち”なところがあります。
以前は、スピードを意識するあまり、確認を省いてしまったり、周囲と進捗のタイミングがずれてしまうことがありました。
その反省から、最近は“スピードより正確性を優先する段階”を明確にし、チェックリストを作成してから作業を進めるようにしています。
その結果、ミスが減り、チーム全体の業務効率も上がりました。
今では“スピードと正確さのバランス”を取ることを意識しています。


具体例②
私は行動が早い反面、少し“せっかち”なところがあります。
とくに、営業活動では、早く結果を出したい気持ちが強く、お客様の検討ペースを待たずに提案を急いでしまったことがありました。
その経験から、“相手の理解度に合わせて進めること”の大切さを学び、今ではヒアリングを丁寧に行い、お客様が安心して判断できるよう意識しています。
結果として、信頼関係を築くスピードが以前よりも早くなりました。
優柔不断


具体例①
私は、チームの方向性を決める際に“優柔不断”な面があり、複数の意見をまとめきれずに判断が遅れることがありました。
その経験から、まず“判断の目的と優先順位”をチームで共有し、その上で各意見のメリット・デメリットを整理してから結論を出すようにしました。
これにより、意思決定のスピードが早まり、メンバーからも“判断基準が明確で動きやすい”と言ってもらえるようになりました。


具体例②
私は、以前仕事の進め方を決める際に“優柔不断”なところがありました。
一例として、ミスを避けたい気持ちが強く、複数の方法を比較しすぎて決定が遅れ、上司や同僚を待たせてしまったことがあります。
その反省から、今では“自分で決められる範囲と、上司に相談すべき範囲”を明確に線引きし、期限を設けて判断するようにしています。
結果として、業務のスピードが上がり、報告のタイミングもスムーズになりました。
マイペース


具体例①
私の短所は“マイペースな性格”です、
以前、自分のペースで仕事を進めすぎて、顧客からの急な要望への対応が遅れることがありました。
その反省から、今では“相手のペースを優先する日”と“自分の計画を進める日”を分けて管理し、臨機応変に対応できるよう工夫しています。
結果的に、お客様から“対応が早くて安心できる”と評価をいただくようになりました。
今では、マイペースさを“安定した行動力”として活かすようにしています。


具体例②
私は“マイペース”な性格で、以前は自分の納得がいくまで時間をかけすぎてしまい、提出が遅れたことがありました。
その経験から、現在は“自分のこだわりポイントをチームで共有する”ことで、方向性を確認しながら進めるようにしています。
また、締め切りの2日前に一度フィードバックをもらうようにした結果、修正が減り、最終的なクオリティも上がりました。
今では、マイペースさを“安定したクオリティを保てる強み”として意識しています。
緊張しやすい


具体例①
私は、人前で話すときに緊張しやすく、以前はプレゼン中に早口になったり言葉が詰まったりしてしまうことがありました。
しかし、発表後に“伝わりにくかった点”を先輩にフィードバックしてもらい、次の発表では“話すスピード”と“目線”を意識して練習を重ねました。
今では、“緊張する=それだけ丁寧に伝えたいという気持ちの表れ”だと考え、資料の構成にも一層工夫するようになりました。
結果として、社内発表会での企画提案が採用されるまでに成長できました。


具体例②
私は“緊張しやすい”性格です。
以前、緊張しやすい性格が原因で上司への報告や重要書類の提出時に焦ってミスしてしまったことがありました。
それ以来、同じ状況を繰り返さないよう、“報告前のチェックリスト”を自作し、声に出して確認する習慣をつけています。
その結果、ミスが減り、上司から“安心して任せられる”と言っていただけるようになりました。
要領が悪い


具体例①
私の短所は“要領が悪い”性格です。
以前、自分の性格が原因で新しい業務やツールの習得に時間がかかることがありました。
しかし、現在はその分一度覚えたことは確実に再現できるよう、手順をマニュアル化して残すようにしています。
その結果、後輩への教育でも同じ資料を活用できるようになり、チーム全体の効率化を実現しています。


具体例②
私は“要領が悪い”ところがあります。
一例として、商談準備に時間がかかり、効率的にスケジュールを組めない時期がありました。
その反省から、よくある質問や提案内容を自分なりにパターン化し、商談の前日に“提案の型”を確認して臨むようにしました。
結果として、準備時間が半分に短縮され、お客様への対応スピードも向上しました。
私は、要領はいい方ではありませんが、その分“継続的に改善していく力”で貴社に貢献します。
拘りが強い


具体例①
私の短所は“こだわりが強い”性格です。
以前、料理や接客の細かい部分にこだわりすぎて、提供スピードが遅れることがありました。
その経験から、チーム内で“こだわる部分と優先する部分”を共有し、役割分担を意識するようにしました。
その結果、サービスの質を保ちながらも回転率やお客様満足度が向上しました。
今では、こだわりをサービスの質を高める原動力として活かせています。


具体例②
私は“こだわりが強い”ところがあります。
以前は、製造ラインで細部のチェックに時間をかけすぎ、全体の作業スピードが落ちたことがありました。
その経験を踏まえ、チェックすべき項目を“重要な部分”に絞り、手順を標準化することで作業効率を改善しました。
その結果、品質を保ちながら生産スピードも向上し、ライン全体の作業効率にも貢献できました。
鈍感


具体例①
私は“鈍感”なところがあります。
前職では、お客様の微妙な反応や表情の変化に気づかず、ニーズを取りこぼしてしまったことがありました。
その反省から、お客様との会話中はメモを取りながら意識的にヒアリングを深めるようにしました。
その結果、ニーズの把握精度が上がり、提案内容の精度も向上。成約率も改善しました。


具体例②
私は“鈍感”な性格で、周囲の些細な批判や雑談にあまり影響を受けません。
前職では、それが裏目に出て、チーム内の小さな問題や改善点に気づかず、作業効率が落ちたことがありました。
そこで、チームミーティングで意見を可視化し、他のメンバーの気づきも取り入れる仕組みを作るようにしました。
その結果、作業効率が改善され、チーム全体でのミスも減りました。
今では、鈍感な性格を冷静に物事を判断したり、集中力を高めたりすることへ活かせています。
プライドが高い


具体例①
私は“プライドが高い”ところがあります。
前職では、自分のアイデアやデザインにこだわりすぎ、チームメンバーの意見を取り入れられないことがありました。
その経験をきっかけに、チームの意見を積極的に聞き、優先順位を明確にしながら修正可能な部分と自分の強みを活かす部分を分けるようにしました。
その結果、チームでの企画承認がスムーズになり、成果物のクオリティも向上しました。


具体例②
私は“プライドが高い”ところがあります。
前職では、自分の設計や作業ミスを認めにくく、指摘されても反発してしまうことがありました。
しかし、その経験を通じて、まず指摘内容を客観的に受け止め、改善策を具体的に整理して取り組むことで、作業精度が向上し、チームメンバーからの信頼も高まりました。


ーまとめー
弱みを「自分を知るためのチャンス」へと変えよう!


今回は、自己分析を通して自分の課題を掘り起こす具体的な方法や考え方について解説しました。
弱みを見つける作業は、決して自分を否定することではありません。
むしろ、「自分を理解し、成長させるための入り口」です。
とくに、転職活動では、強みだけでなく、弱みをどう受け止めて行動してきたかが求められます。
この記事を参考に、自分の弱みを正しく掘り起こし、前向きに転職活動を進めましょう。
自己分析をはじめとした転職活動および就職活動に役立つサービスをお探しの方は、こちらの記事をご覧ください。
![]()
![]()
まとめ
弱みを「自分を知るためのチャンス」へと変えよう!


今回は、自己分析を通して自分の課題を掘り起こす具体的な方法や考え方について解説しました。
弱みを見つける作業は、決して自分を否定することではありません。
むしろ、「自分を理解し、成長させるための入り口」です。
とくに、転職活動では、強みだけでなく、弱みをどう受け止めて行動してきたかが求められます。
この記事を参考に、自分の弱みを正しく掘り起こし、前向きに転職活動を進めましょう。
自己分析をはじめとした転職活動および就職活動に役立つサービスをお探しの方は、こちらの記事をご覧ください。
![]()
![]()
-1024x341.webp)
-1024x341.webp)
\ 新卒求人サイト /
.webp)
.webp)
\ 新卒求人サイト /


\ 生鮮業界求人サイト /


\生鮮業界求人サイト/


\ 整備士求人サイト /
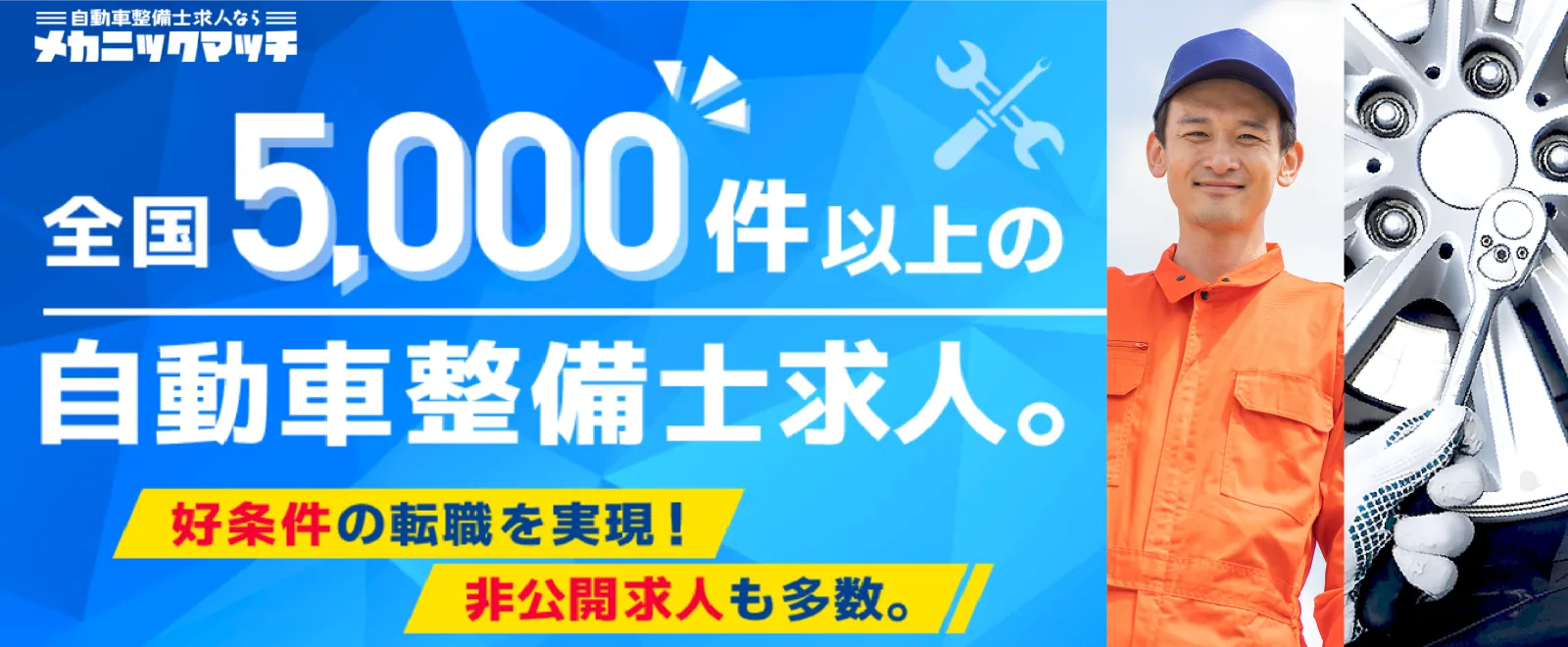
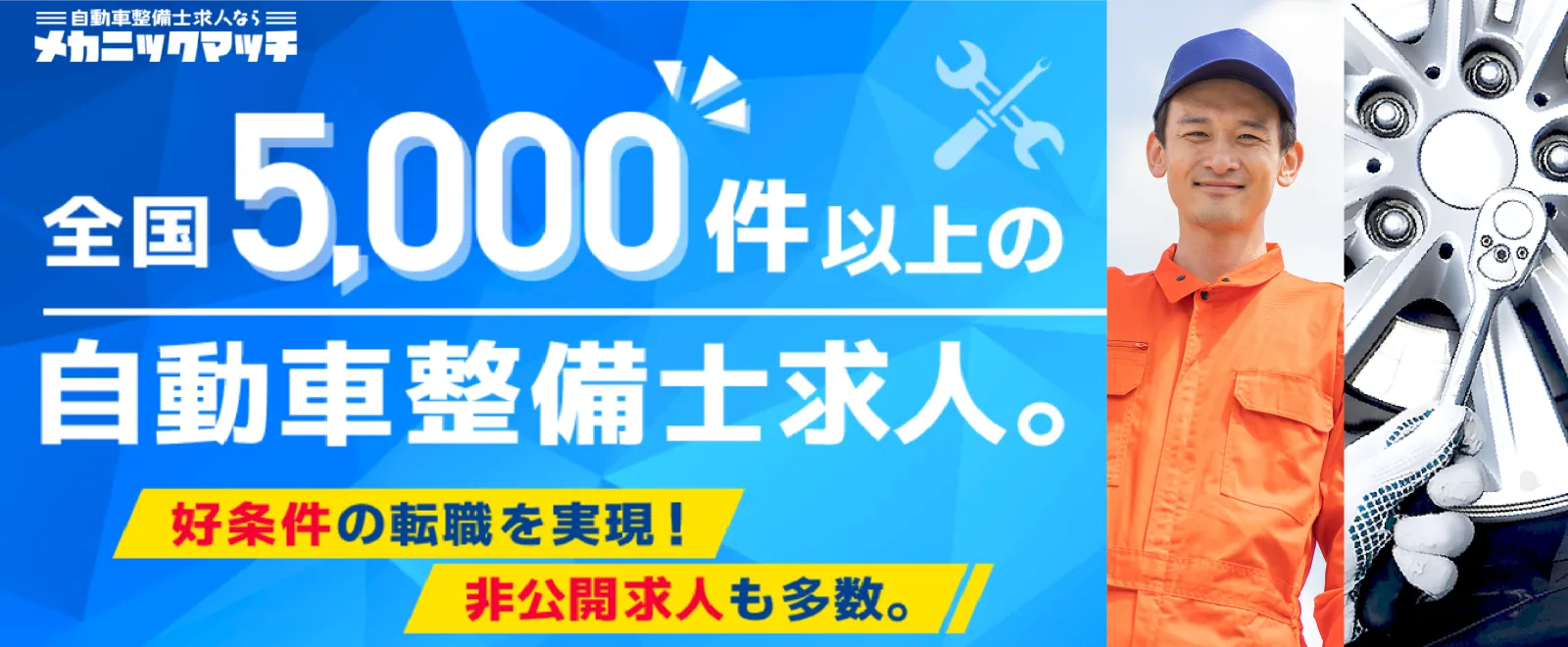
\ 整備士求人サイト /


\ 寿司職人求人サイト /


\ 寿司職人求人サイト /

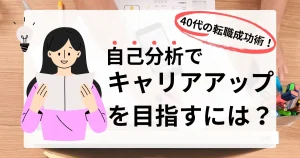
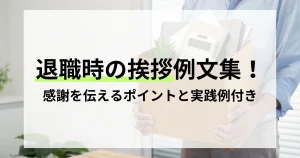


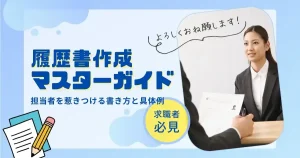

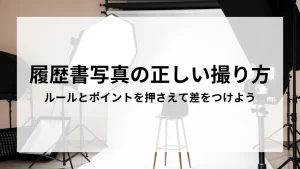
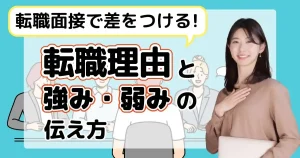
-.webp)