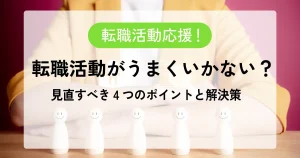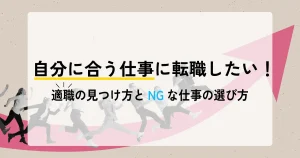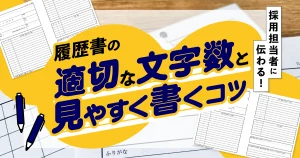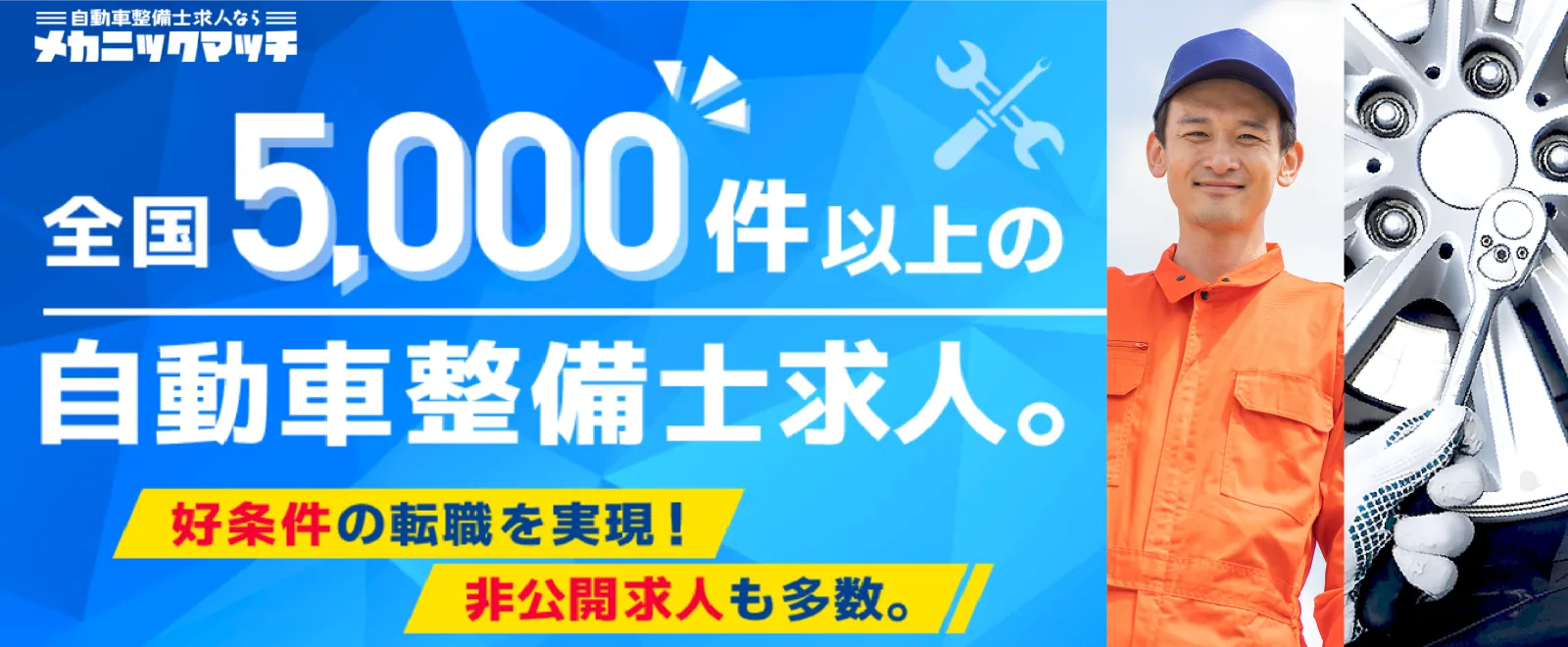厚生労働者が実施している「令和2年転職者実態調査の概況」によると、2020年10月1日時点で一般労働者に対する転職割合は、7.2%とされています。
また、起業やフリーランスなど働き方が増えていることなどが原因で、今の職業から別のキャリアを歩もうとする機会が増えています。
そのため、今後、退職届や退職願を提出する機会があるかもしれません。
しかし、退職届や退職願をどのように書けばいいか分からないという方も少なくないでしょう。
本記事では、退職届や退職願の書き方や、出すタイミングなどを紹介します。
この記事を参考に、スムーズなキャリアチェンジを実現しよう!

退職届とは

退職届とは、退職する意思を会社に正式に通知するための書類です。
退職の意思が固まった後に提出し、退職の希望日などを明示します。
口頭での申し出も可能ですが、書面での提出により意思の明確化や証拠になります。
会社の規定に従い、適切な提出先を確認してから提出することが重要です。
退職願との違い

退職願とは、退職の意思を会社に申し出るための書類です。
直属の上司に提出します。
退職願は、口頭でも可能ですが、書面での提出は意思の強さを示すための根拠になります。
退職届と退職願の違いは、退職の意思表示の方法です。
退職届は、「自主退職」を示すものです。
労働者が一方的に退職の意思を通告します。
会社の同意を待たずに効果が生じるため、提出後の撤回は基本的にできません。
一方、退職願は、「合意退職」を申入れるものです。
労働者が会社に対して退職の了承を求めます。
退職願は、会社の承諾が得られなければ、退職の効果は生じません。
そのため、退職願は撤回可能で、円満に退職を進めたい場合に適しています。
辞表との違い

辞表とは、社長や取締役などの役職を辞めるために提出する書類です。
辞任の意思を正式に示します。
公務員の場合も、辞表は退職届として扱われます。
退職届と辞表の主な違いは、使用される場面です。
退職届は、一般社員が労働契約を終了するために提出するものです。
会社に対して退職の意思を伝え、契約を解除する手続きの一環です。
退職届は、通常、直属の上司または人事部に提出します。
一方、辞表は、役員や公務員が役職を辞任する際に提出するものです。
役職を辞める意思を正式に示します。
辞表を提出することで、役職から外れることを報告しますが、一般社員として勤務を続ける場合もあります。
退職届や退職願の正しい書き方

ここからは、退職届や退職願を作成する時のポイントを8つ紹介します。
書き出し
私儀(わたくしぎ)は、個人的な事情を述べる際に使う言葉です。
ビジネスシーンでは主に辞表や手紙で用いられます。
個人の事情であることを示し、敬意を表すために使います。
退職届や退職願の書き出しは、私儀や自分個人や私生活に関したことを表す「私事(わたくしごと)」と記載します。
退職理由
退職届や退職願には、退職理由を記載しましょう。
退職届や退職願に記載する退職理由は、自己都合か会社都合によって異なります。
自己都合で退職する場合、退職理由は「一身上の都合」とするのが一般的です。
一身上の都合は、個人的な理由で退職することを示すもので、具体的な理由は省略されます。
これに対し、会社都合で退職する場合は、具体的な理由を記載することが重要です。
一例として、「業績不振による倒産」や「組織改編による部門縮小」などが該当します。
退職理由は、雇用保険の給付条件や転職活動にも影響を与えるため、正確な記載が求められます。
退職日
退職届や退職願に記載する退職日は、会社の規定や慣習によって異なります。
一般的には、雇用契約が終了する日が退職日です。
しかし、会社によっては最終出勤日を退職日とする場合もあります。
また、退職日を月末や締め日に設定できる会社もありますが、多くの場合は月末退職が選ばれるでしょう。
雇用保険の手続きや社会保険料の計算の関係から、退職日を月末にすることが一般的です。
退職届や退職願の日付は、縦書きの場合は漢数字、横書きの場合は算用数字で記入し、西暦または和暦で統一しましょう。
文末
退職願は、依頼の姿勢を示し、退職届は確定的な意思を示します。
退職願の文末では、退職の意向を丁寧に伝えます。
そのため、丁寧に「退職いたしたくお願い申し上げます」と記載します。
一方、退職届は、退職が承諾された後の正式な報告です。
そのため、「退職いたします」と宣言します。
届出年月日
退職届や退職願に記載する届出年月日は、実際に上司に提出する日付です。
届出年月日は、退職日とは異なります。
届出年月日を記載する場合は、縦書きの場合は漢数字、横書きの場合は算用数字を使用してください。
また、年の表記は西暦または和暦で統一しましょう。
退職届を郵送する場合は発送日を記載し、手渡しの場合は渡す日が提出日となります。
一度提出した退職届の日付は原則として変更できません。
しかし、どうしても変更が必要な場合は、上司と相談の上、再度作成しましょう。
所属
退職届や退職願を提出する場合は、行の下部に正式名称で記載してください。
辞表とは異なるため、役職は記載しなくても構いません。
氏名
退職届や退職願を作成する場合は、フルネームを記載しましょう。
氏名の末尾には、認め印を押しましょう。
シャチハタは避けてください。
宛名
退職届や退職願の宛先には、会社の最高執行責任者である代表取締役社長などの役職名と名前を記載しましょう。
また、宛先は、自分の名前より上に位置させてください。
「様」も使用可能ですが、ビジネス文書では「殿」がより正式な敬称とされています。
退職するまでの流れ

ここからは、退職する際にどのタイミングで退職届や退職願を提出すべきかを紹介します。
退職の意思を固める
退職の意思を固める際には、
辞める理由と目的を再確認することが重要です。
感情的な判断で退職を決めるのではなく、上司や人事に相談して他の解決策がないか考えましょう。
また、転職先が決まってから退職するか、退職後に転職活動を始めるかの選択肢も考慮してください。
それぞれのメリット・デメリットを理解しておくことが大切です。
転職活動中の不安や焦りを避けるためにも、冷静に判断して行動することが求められます。
退職願を提出する
退職願を提出する際は、いくつか注意しなけれなばりません。
まず、封筒は白無地を使用し、退職願が折れないように適切なサイズを選びましょう。
白無地の封筒などは、100円均一ショップなどでも購入可能ですが、会社で指定されているものがあればそちらを使用しましょう。
また、退職願はフォーマットに従って作成してください。
PCでの作成も可能ですが、黒ボールペンで手書きするのが基本です。
クリアファイルに入れて持参すると、汚れや折れを防ぎます。
![]()
退職願は直属の上司に直接渡し、感謝の気持ちを伝えることが大切です。
退職日を決める
退職日を決める際は、次の転職先が決まっているかどうかを確認しましょう。
転職先が決まっている場合、退職日はその入社日の前日が理想です。
入社日が未確定の場合は、賞与や退職金のタイミング、有給休暇の消化、就業規則、引き継ぎの状況を考慮して退職日を決めてください。
賞与をもらってから退職する、引き継ぎを十分に行うために余裕を持つなど、自分の状況に合わせて慎重に決めましょう。
退職届を提出する
退職届を提出する際は、
就業規則を確認し、退職届を提出する相手や期日を把握しましょう。
一般的には、直属の上司に退職希望日の1〜2カ月前までに提出することが求められます。
提出方法としては、メールや郵送の指定がなければ、会議室などのプライベートな場所で直接手渡すのがマナーです。
退職届を提出する前に、会社の就業規則を確認し、正しい手続きやタイミングを守りましょう。
労働契約を解除する
退職届が受理された後、正式な手続きを進めます。
業務の引き継ぎを完了し、必要な書類を整えましょう。
民法第628条によると、契約期間が定められている場合は、契約満了を待つか、正当な理由がある場合のみ早期解除が可能とされています。
第六百二十八条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約を解除できる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。引用元:民法 | e-Gov 法令検索
また、契約解除後は、退職届や必要な書類を整え、離職票などの受け取りを確認することも重要です。
退職届や退職願を郵送で提出できるのか

一般的に退職届や退職願は、手渡しが基本とされていますが、退職届や退職願を郵送で提出できます。
精神的・肉体的な不調、引越しや入院などの特別な事情がある場合や、会社から郵送の指示があった場合は、郵送での提出がおすすめです。
郵送する際は、事前に直属の上司や人事部門に連絡し、適切な封筒を使い、添え状を同封するのがマナーです。
これにより、会社に対する礼儀を保ちつつ、スムーズな退職手続きを進められます。
退職の切り出すときのポイント

退職届や退職願を提出するためには、勤めている企業へ退職を切り出さなければなりません。
転職や退職を検討している方の中には、どうやって退職を切り出せばいいか分からないという方も少なくないでしょう。
ここからは、退職を切り出すときのポイントを3つ紹介します。
直属の上司に伝える
企業に退職の意思を伝えたい場合は、直属の上司に伝えましょう。
不確定な情報が先に同僚や取引先に伝わると、混乱を招くかもしれません。
上司は日々の業務を直接管理しています。
直属の上司に伝えることで、上司がチームや業務への影響を考慮して適切に段取りを組めます。
そのため、最初の段階で退職の意思を口頭で伝え、上司との合意を得た後に、上位役職者や人事部に段階的に報告することが一般的です。
また、退職の意思が固まっていない段階で他の人に伝えると、後に退職日が変更されたり、退職自体が撤回されたりする可能性があります。
こうした手順を踏むことで、退職の意思がスムーズかつ正式に受け入れられます。
相手と2人きりの場所で伝える
退職は、非常にデリケートな話題です。
そのため、直属の上司などの退職の意思を伝えたい相手と2人きりの場所で伝えましょう。
相手の都合を確認し、対面で冷静に話ができる環境を整えることが重要です。
会議室など、話し声が漏れずプライバシーが保たれる場所を選び、上司に対して真剣な意思を示しましょう。
また、食事の席や終業後のお酒の席など、カジュアルな環境ではなく、正式な場を設けることで、退職の意思が真剣に受け取られることを促進します。
さらに、二人きりで話すことで、上司が退職の影響を考慮し、適切な対応策を準備する時間を確保できます。
テレワークの場合でも、Web会議ツールや電話を活用し、対面での冷静なコミュニケーションを維持することが重要です。
これにより、退職の意思が円滑に伝わり、相互理解が深まります。
強い意思を持っていることをアピールする
退職の意志を切り出す際は、退職の意思が強いことを明確に伝えましょう。
引き留められることを想定し、その場で揺るがない姿勢を示すことが求められます。
「引き留めていただけるのはありがたいが、退職の意思は変わらない」という態度を一貫して保ちましょう。
また、具体的で納得できる退職理由を準備しましょう。
あいまいな理由ではなく、

今とは別の業界に行きたい



この会社では実現できない目標がある
など、現在の職場では実現しない明確な理由を提示してください。
退職後にやりたいことを明確にすることで、引き留めにくくなります。
退職の引き止めに合わないための対処法


退職の意思を示しても、スムーズに受理されないことがあります。
ここからは、退職の引き止めに合わないための対処法を紹介します。
就業規則や法律を確認する
退職の引き止めに合わないためにも就業規則や法律を確認しましょう。
就業規則に退職を制限する規定があっても、その強制力は限定的です。
日本国憲法第22条では、「職業選択の自由」が保障されており、これに反する退職の禁止規定は無効となります。
第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
就業規則で退職時期を「3か月前に通知すること」と定めても、民法では退職の申し入れから2週間で雇用契約が終了すると規定されています。
従って、就業規則よりも民法が優先されるため、従業員は2週間後に退職する権利を持ち、会社がそれを強制的に延長することはできません。
就業規則や法律を確認し、円満退職を目指しましょう。
業務をしっかり引き継ぐ
円満に退職するためには、業務をしっかり引き継ぐことが重要です。
法律上の義務はありません。
しかし、労働契約による業務命令権によって、契約上の義務となります。
退職日までの業務遂行は労働者としての義務であり、引き継ぎも正当な業務命令の一部です。
会社側は引き継ぎを命じる権限を持ち、引き継ぎが不十分だと業務に支障が出る可能性があります。
そのため、しっかりと引き継ぐことで後任者がスムーズに業務を引き継ぎ、会社に迷惑をかけないことが求められます。
退職の引き止めにおける法律について


労働者は、民法で退職する自由が認められており、退職のタイミングは労働契約の種類によって異なります。
有期雇用契約の場合、契約期間中の退職は原則として認められません。
しかし、「やむを得ない事由」があれば退職可能です。
無期雇用契約の場合、労働者は2週間前に退職の意思を告げることで退職できることが民法627条1項で定められています。
第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約を申入れられる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
また、会社が退職を引き止めるために下記のような手段を取ることは、違法となる可能性があります。
- 後任がいないから退職を受理できないと伝える
- 給料や退職金を支払わない
- 有給消化を認めない
- 離職票を発行しない
- 懲戒解雇する
- 損害賠償を請求する
過剰な引き止めを受けた場合は、適切な証拠を集め、必要に応じて弁護士に相談してください。


ーまとめー
正しい手続きを踏んで、円満退職を目指そう


今回は、退職届や退職願の書き方や、出すタイミングなどを紹介しました。
円満退職により良好な関係を維持することで、再雇用や推薦、業界内での評判を良好に保てます。
また、法的トラブルや不必要な対立を避けることにもつながるでしょう。
正しい書き方で作成した退職届や退職願を適切なタイミングで提出し、円満退職を目指しましょう。
![]()
![]()
まとめ
正しい手続きを踏んで、円満退職を目指そう


今回は、退職届や退職願の書き方や、出すタイミングなどを紹介しました。
円満退職により良好な関係を維持することで、再雇用や推薦、業界内での評判を良好に保てます。
また、法的トラブルや不必要な対立を避けることにもつながるでしょう。
正しい書き方で作成した退職届や退職願を適切なタイミングで提出し、円満退職を目指しましょう。
![]()
![]()